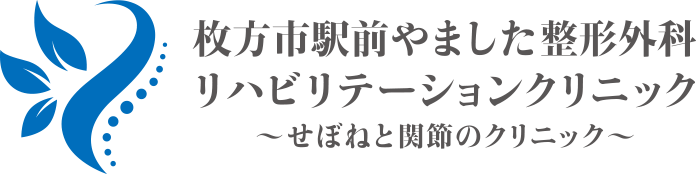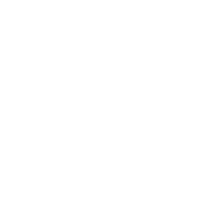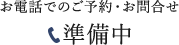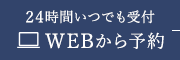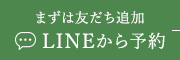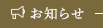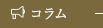手首が痛い症状は
ありませんか?
以下のような症状がありましたら、当院までご相談ください。
- 手をひねったあとから、ずっと手首が痛い
- ドアノブを回すとズキッとする
- 朝起きたときが一番痛くて、手がこわばって動かしにくい
- 子どもを抱っこしたときに痛くて支えられない
- 物を持ち上げようとすると手首に痛みが走る
- ずっとパソコン作業をしていたら、手首がジンジンする
- 腱が突っ張るような痛みで、動かすのが怖い
- 痛いところを押すと、ズーンとした痛みがある
- 手首を反らすと痛いけど、曲げるとそうでもない
- 親指の付け根から手首のあたりが痛む
- 洗濯物を絞る動作がとてもつらい
- 最近、腫れてきて見た目でも左右差がわかる
- サポーターをしていないと不安で使えない
- 階段の手すりをつかむと痛くて力が入らない
- ペットボトルのふたを開けるときに激痛が走る
- 少し使うだけで痛みがぶり返す感じがする
- 書き物をするときに手首が痛くて長く続けらない
- しばらく使わないでいるとマシになるけど、また使うと痛くなる
- 痛みと一緒に手がしびれる
- サッと手を動かしたときにピキッと痛む瞬間がある
など
手首が痛い原因
手根管症候群
手根管とは、手首の内側にあるトンネル状の空間で、正中神経や腱が通っています。この部分で神経が圧迫されると、親指から薬指にかけてしびれや痛み、違和感が現れます。特に夜間や朝方に症状が強く出ることがあり、手を振ったりすると少し楽になることもあります。進行すると、つまみ動作がしづらくなったり、筋力低下を感じることがあります。よく手をつく方、透析治療を受けている方、更年期の女性や妊娠中の方、手をよく使う作業をする人に多く見られます。
ドケルバン病(狭窄性腱鞘炎)
親指を動かす腱が通る腱鞘というトンネルに炎症が起き、親指の付け根から手首にかけて痛みが出る病気です。物をつかんだり、ドアノブを回したりする動作で痛みが増すのが特徴です。スマホの使いすぎや育児、家事、手作業の多い仕事をする人に起こりやすく、親指を内側に握って手首を小指側に倒すことで強い痛みが誘発される場合は、この病気が疑われます。
腱鞘炎(けんしょうえん)
腱鞘炎は、腱とその周りを包む鞘に炎症が生じることで起こります。手首の使いすぎが原因となり、特に反復的な動作が多い人に見られます。症状としては、手首を動かすと痛みが強くなり、腫れや熱感も感じることがあります。例えば、パソコン作業や料理、楽器演奏などで長時間手を使うことが影響します。痛みを避けるために、作業の中で手首を休めることが重要です。
ガングリオン
ガングリオンは、手首にできる良性の腫瘍で、関節や腱鞘から出てきた液体が袋状に溜まることで発生します。腫れが目立ち、触れるとしこりを感じることがありますが、痛みを感じることは少ないです。しかし、腫瘍が神経や血管に圧迫を加えると、痛みやしびれを引き起こすこともあります。放置しても特に問題ないことが多いですが、腫れが大きくなったり痛みが強くなる場合には手術を検討することがあります。
関節リウマチ
関節リウマチは、免疫系の異常によって自己の関節を攻撃してしまう自己免疫疾患で、特に手や手首に影響を与えることがあります。朝方のこわばりや、休息後に痛みが強くなるのが特徴です。手首に限らず、複数の関節に痛みが生じ、炎症が進行すると関節が変形することもあります。放置すると日常生活に支障をきたすことがあり、早期に治療を開始することが重要です。
手首の小指側が痛い原因は?
小指側の腱鞘炎(TFCC損傷)
小指側の手首の痛みは、三角線維軟骨複合体(TFCC)の損傷や炎症が原因であることがあります。TFCCは、手首の小指側に位置する軟骨で、手首の安定性を保つ役割を果たしています。この部位が損傷すると、小指側に痛みが出ることが多く、特に手首をひねったり、重いものを持ったりすると痛みが増します。TFCC損傷は、スポーツや手首を多く使う作業で起こりやすいです。
小指側の手根骨骨折
小指側の手首に痛みがある場合、手根骨の一部である小指側の手根骨(尺側手根骨)が骨折している可能性があります。転倒や手をついた際に衝撃が加わり、骨折することがあります。痛みは急激で、腫れや青あざが見られることがあります。手首を動かすときに痛みが強くなることが特徴です。
腱鞘炎(尺側)
手首の小指側には、尺側に位置する筋肉をつかさどる腱が通っており、その腱に炎症が生じることがあります。これは、繰り返し手首を使ったり、手首を無理に動かしたりすることで起こることが多いです。特に、パソコン作業やスポーツで手首を頻繁に使う場合に発症することがあります。
末梢神経の圧迫
(尺骨神経障害)
手首の小指側の痛みは、尺骨神経の圧迫や障害が原因となることもあります。尺骨神経は手首の内側を通り、小指と薬指の感覚や運動を司ります。圧迫されると、手首の小指側に痛みやしびれ、感覚の鈍さが現れることがあります。この症状は、手首や肘の使い過ぎや、長時間同じ姿勢を保つことが原因となることがあります。
手首の外側が痛い原因は?
橈骨神経障害(手根管症候群)
手首の外側に痛みを感じる場合、橈骨神経(とうこつしんけい)の圧迫や障害が原因であることがあります。橈骨神経は手首の外側を通り、手指の動きに関与しています。手首を長時間使い過ぎたり、繰り返し同じ動作を行ったりすると、神経が圧迫されて痛みやしびれ、麻痺を引き起こすことがあります。
腱鞘炎
(尺側手根伸筋腱腱鞘炎)
手首の外側には、尺側手根伸筋腱など、指を伸ばす役割を持つ筋肉が通る腱鞘があります。これらの腱鞘に炎症が起きることで痛みが生じることがあります。特に、手首を多く使うスポーツやパソコン作業、重い物を持つ動作を繰り返すことで腱鞘炎が発生します。この炎症が手首の外側に痛みを引き起こします。
肘部管症候群
(手首の外側の神経障害)
手首の外側に痛みがある場合、肘部管症候群も考えられます。肘部管は、肘にある神経の通り道が細くなっている状態で、ここが圧迫されることにより痛みが生じることがあります。特に尺骨神経が圧迫されることで、手首の外側に痛みを感じることがあります。肘を過剰に使用することや、肘を長時間動かし続けることが原因となることが多いです。このように一見、関係ないところに原因があったりします。自己判断せずに整形外科を早めに受診することが重要です。
TFCC損傷
(手首の三角線維軟骨複合体の損傷)
手首の外側に痛みを感じるもう一つの原因として、手首のTFCC(三角線維軟骨複合体)の損傷があります。これは、手首の内側に位置する軟骨の損傷ですが、損傷が進行すると手首全体に痛みを感じることがあります。特に手首を回したり、ひねったりする動作で痛みが増すことが特徴です。これも手首を頻繁に使用する仕事やスポーツに関連しています。
外側上顆炎(テニス肘)
手首の外側の痛みが、肘に関連している場合があります。外側上顆炎(テニス肘)は、肘の外側の腱が炎症を起こす病気ですが、その痛みが手首に放散することがあります。手首を動かす際に痛みが増すことが特徴で、テニスやゴルフなど、肘を使うスポーツで見られることがありますが、スポーツに関係なくでることも多くあります。
手首が痛いときの検査・診断
問診

医師はまず、痛みの発生時期、強さ、痛む部位、使い過ぎや外傷があったかどうかを詳しく聞きます。また、手首を動かすことで痛みが増すかどうか、生活習慣や仕事の影響についても確認されます。
視診・触診

手首を目で見て、腫れや変形がないか、発赤や熱感などがあるかを確認します。触診によって、痛みの原因となる部位を特定します。
X線検査(レントゲン)
 骨折や関節の変形、関節内の異常を確認するためにレントゲンを撮影します。手首の骨に異常がないかを調べる基本的な検査です。
骨折や関節の変形、関節内の異常を確認するためにレントゲンを撮影します。手首の骨に異常がないかを調べる基本的な検査です。
MRI検査
 軟部組織の損傷を診断するために、MRI(磁気共鳴画像法)を使用することがあります。必要な場合には、連携する医療機関をご紹介いたします。
軟部組織の損傷を診断するために、MRI(磁気共鳴画像法)を使用することがあります。必要な場合には、連携する医療機関をご紹介いたします。
超音波検査(エコー)
 軟部組織の炎症や損傷を評価するために、超音波を使って手首を検査することもあります。特に腱の炎症や滑液包炎などを発見するのに有効です。
軟部組織の炎症や損傷を評価するために、超音波を使って手首を検査することもあります。特に腱の炎症や滑液包炎などを発見するのに有効です。
神経伝導速度検査(NCS)
手首の痛みが神経に関連している場合、神経伝導速度を測定することで、神経障害があるかどうかを調べます。手首の痛みが手根管症候群に関連している場合に有効です。
血液検査
 炎症が関与している場合や、感染症や自己免疫疾患(例えば、関節リウマチなど)の可能性を調べるために血液検査を行うことがあります。
炎症が関与している場合や、感染症や自己免疫疾患(例えば、関節リウマチなど)の可能性を調べるために血液検査を行うことがあります。
手首が痛いときの治療・対処法
安静
手首の痛みが軽度であれば、まずは安静にすることが最も重要です。無理に手首を使わないように心掛け、過度な動作を避けることで回復を早めることができます。
アイスパック(冷却)
急性の痛みや腫れがある場合、アイスパックを手首に当てることで、炎症を抑え、痛みを軽減することができます。凍傷に気をつけながら15〜20分程度冷やすと効果的です。特に、腱鞘炎や靭帯損傷などの炎症がある場合に有効です。
圧迫・固定
手首を動かさないように固定するために、サポーターや包帯で軽く圧迫をかけることがあります。これにより腫れや痛みの軽減が期待できます。外的な衝撃から手首を守るため、軽度の固定も役立ちます。
温熱療法
炎症が治まりかけてきた段階で、温熱療法(ホットパッドや温かいタオル)を使用すると、血行を促進し、痛みを和らげることができます。慢性の痛みには有効な方法です。
薬物療法
痛みや炎症がひどい場合には、鎮痛剤(アセトアミノフェンなど)や抗炎症薬(NSAIDs)を使用することがあります。これらは痛みを軽減し、炎症を抑える働きがあります。
理学療法
痛みが長引く場合や、筋力の低下が見られる場合には、理学療法が効果的です。物理療法(温熱療法や電気療法)や、リハビリテーションを通じて、手首を強化し、回復を促進します。
ステロイド注射
慢性的な炎症や腱鞘炎の場合、ステロイド注射を行う場合があります。これにより、強力な抗炎症効果が得られ、痛みが軽減します。ただし、頻繁には使用できないため、他の治療との組み合わせが重要です。
手術
保存療法(安静やリハビリテーションなど)で改善しない場合、手術が検討されることもあります。例えば、神経・腱鞘炎が重度で進行している場合や、靭帯が断裂している場合などです。手術によって損傷した部位を修復します。手術が必要な場合には、連携する医療機関をご紹介いたします。
生活習慣の見直し
痛みの原因が姿勢や過度の負担に関連している場合、仕事や趣味の内容を見直すことが必要です。例えば、スマホやパソコンの使用時に手首の角度に注意する、手首に負担がかからないような作業方法を取り入れることが大切です。
手首の痛みを
放っておくとどうなる?
 手首の痛みを放っておくと、さまざまな悪影響を引き起こす可能性があります。まず、痛みが悪化し、炎症が進行することで痛みが増し、日常生活に支障をきたすことがあります。さらに、手首の可動域が制限され、物をつかむ動作や手首を動かすことが難しくなります。放置すると、急性の炎症が慢性化し、治療に長期間を要することがあります。慢性化すると、最終的には手術などの治療が必要になる場合もあります。
手首の痛みを放っておくと、さまざまな悪影響を引き起こす可能性があります。まず、痛みが悪化し、炎症が進行することで痛みが増し、日常生活に支障をきたすことがあります。さらに、手首の可動域が制限され、物をつかむ動作や手首を動かすことが難しくなります。放置すると、急性の炎症が慢性化し、治療に長期間を要することがあります。慢性化すると、最終的には手術などの治療が必要になる場合もあります。
また、手首をかばって動かすため、他の部位に負担がかかり、二次的な痛みを引き起こすこともあります。手首の痛みが続くと、生活の質が低下し、仕事や趣味、家事などの日常的な活動が困難になることもあります。放置していると、関節の変形や軟骨の損傷が進行し、手術が避けられなくなることもあるため、早期の診断・治療が重要です。