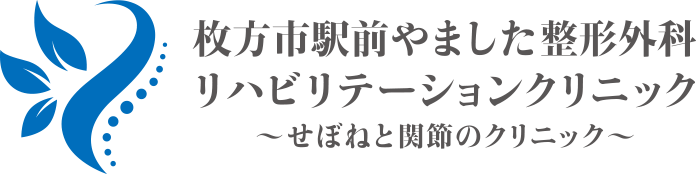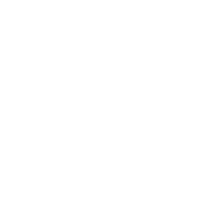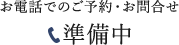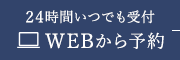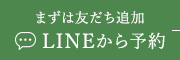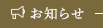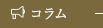腱鞘炎(けんしょうえん)とは
 腱鞘炎は、腱とその腱を覆う腱鞘という組織に炎症が起こることで、痛みや 運動障害を引き起こす疾患です。主な原因は、手や指の使いすぎによる慢性的な摩擦によるものが多く、パソコン作業、スマートフォン操作、スポーツ、楽器演奏、手作業の多い仕事などが誘因となります。女性ホルモンの変動や加齢、関節リウマチなどの基礎疾患が関与することもあります。典型的な症状は、手首、手のひら、指の付け根などの痛みで、動作時や押した際に増強します。腫れや熱感を伴うこともあり、進行すると指がスムーズに動かせなくなる、いわゆる「ばね指」と呼ばれる状態になることもあります。 運動障害により、日常生活における細かい作業が困難になることもあります。このような症状があればお気軽に当院を受診してください。
腱鞘炎は、腱とその腱を覆う腱鞘という組織に炎症が起こることで、痛みや 運動障害を引き起こす疾患です。主な原因は、手や指の使いすぎによる慢性的な摩擦によるものが多く、パソコン作業、スマートフォン操作、スポーツ、楽器演奏、手作業の多い仕事などが誘因となります。女性ホルモンの変動や加齢、関節リウマチなどの基礎疾患が関与することもあります。典型的な症状は、手首、手のひら、指の付け根などの痛みで、動作時や押した際に増強します。腫れや熱感を伴うこともあり、進行すると指がスムーズに動かせなくなる、いわゆる「ばね指」と呼ばれる状態になることもあります。 運動障害により、日常生活における細かい作業が困難になることもあります。このような症状があればお気軽に当院を受診してください。
ドケルバン病と腱鞘炎の違い
ドケルバン病と腱鞘炎は、どちらも腱と腱鞘の炎症によって痛みが生じる病気ですが、炎症が起こる部位と関与する腱に違いがあります。
腱鞘炎
腱鞘炎は、広範な用語であり、全身の様々な部位の腱鞘に起こる炎症の総称です。手指の付け根に起こるばね指や、手首の親指側に起こるドケルバン病も、広い意味では腱鞘炎の一種と言えます。症状としては、炎症部位の痛み、腫れ、 運動障害などが共通して見られます。
ドケルバン病
ドケルバン病は、手首の親指側にある、長母指外転筋腱と短母指伸筋腱という2つの腱が通る腱鞘に起こる腱鞘炎の名前です。
特徴的な症状として、親指を広げたり、手首を小指側に曲げたりする動作で、手首の親指側に強い痛みが生じます。腫れや熱感を伴うこともあり、進行すると親指の運動が制限されることがあります。
上記のように、腱鞘炎は様々な場所で起こりうる腱と腱鞘の炎症を指す包括的な言葉であるのに対し、ドケルバン病は手首の親指側の特定の腱と腱鞘に限局した、より具体的な病名となります。どちらも当院にて診察可能ですのでお気軽にご相談ください。
ばね指と腱鞘炎の違い
ばね指は、腱鞘炎の一種でありながら、特有の症状と発生機序を持つため、一般的な腱鞘炎とは区別することが一般的です。
ばね指
ばね指は、指の付け根にある腱鞘で炎症が起こり、腱がスムーズに腱鞘を通過できなくなることで発生します。炎症により腱が肥厚したり、腱鞘が狭窄したりすることで、指を曲げ伸ばしする際に引っかかりが生じ、「カクン」と音がしたり、ばねのように跳ね返ったりする特有の動き(弾発現象)が見られます。進行すると、完全に指が曲がったまま伸びなくなったり、逆に伸びたまま曲がらなくなったりすることもあります。痛みは指の付け根に強く感じることが多いですが、指先や手のひらに放散することもあります。
腱鞘炎
腱鞘炎は、腱とその腱を覆う腱鞘という組織に炎症が生じることで、痛みや腫れ、運動障害を引き起こす状態全般を指します。手のひらや手首など、様々な部位に起こりえます。原因は、使いすぎによる摩擦や、ホルモンバランスの変化、関節リウマチなどが挙げられます。
このように、腱鞘炎は広範な概念であるのに対し、ばね指は指の屈筋腱とその腱鞘に特化した腱鞘炎であり、弾発現象という特徴的な症状を伴います。発生部位は主に指の付け根であり、症状の現れ方にも違いが見られます。どちらも当院にて診察可能ですのでお気軽にご相談ください。
腱鞘炎の原因
 腱鞘炎の主な原因は、腱と腱鞘間の慢性的な摩擦と負担の蓄積です。これは、特定の動作の繰り返しや、手の繰り返しの使用によって引き起こされます。例えば、長時間のパソコン作業やスマートフォンの操作、キーボードやマウスの連続使用は、指や手首の腱に絶え間ない負担をかけ、腱鞘との摩擦を増大させます。
腱鞘炎の主な原因は、腱と腱鞘間の慢性的な摩擦と負担の蓄積です。これは、特定の動作の繰り返しや、手の繰り返しの使用によって引き起こされます。例えば、長時間のパソコン作業やスマートフォンの操作、キーボードやマウスの連続使用は、指や手首の腱に絶え間ない負担をかけ、腱鞘との摩擦を増大させます。
また、スポーツや楽器演奏も腱鞘炎の一般的な原因です。テニス、野球、ゴルフなどの手首や指を酷使するスポーツや、ピアノ、ギターなどの指を細かく動かす楽器演奏は、特定の腱に集中的な負荷を与え、炎症を引き起こしやすくなります。日常生活においても、育児における抱っこや家事での手の酷使、工場でのライン作業など、反復的な手作業が多い仕事も原因の一つとなりうります。
さらに、女性ホルモンの変動も腱鞘炎の重要な要因の一つです。妊娠・出産期や更年期には、ホルモンバランスの変化により腱や腱鞘がむくみやすくなり、摩擦が生じやすくなります。加齢による腱鞘の変性も、腱の滑りを悪くし、炎症のリスクを高めます。関節リウマチや糖尿病などの基礎疾患も、腱や腱鞘の炎症を引き起こしやすい状態を作り出すことがあります。
これらの要因が単独で、あるいは複合的に作用することで、腱鞘に炎症が生じ、腱鞘炎を発症します。予防のためには、手の使いすぎを避け、適度な休息やストレッチを取り入れることが重要です。
ストレスで腱鞘炎になる?
 ストレスが直接的な原因として腱鞘炎を引き起こすというよりは、間接的な要因として関与する可能性が指摘されています。
ストレスが直接的な原因として腱鞘炎を引き起こすというよりは、間接的な要因として関与する可能性が指摘されています。
ストレスを感じると、筋肉が緊張しやすくなります。特に首や肩周りの筋肉が緊張すると、その影響が腕や手首にまで及び、腱や腱鞘への負担を増大させる可能性があります。また、ストレスによって自律神経が乱れると、血行が悪くなり、腱や腱鞘への栄養供給が滞り、回復が遅れることも考えられます。
さらに、ストレスは手の使い方にも影響を与えることがあります。例えば、イライラしながら強くキーボードを叩いたり、無意識に手に力を入れたりするような動作が増えることで、腱や腱鞘に余計な負担がかかることがありうります。
ただし、腱鞘炎の直接的な原因はやはり手の使いすぎや反復動作であると言えます。ストレスは、これらの直接的な原因に拍車をかけたり、症状を悪化させたりする要因として捉えるのが適切でしょう。ストレスを管理し、心身の緊張を和らげることは、腱鞘炎の予防や症状軽減にも繋がる可能性があります。適度な運動、ストレッチなどがストレス緩和に効果的です。当院ではこういった生活指導はリハビリテーションで行いますので、お気軽にご相談ください。
腱鞘炎の初期症状
- 指の付け根や手首に動かし始めに痛みや違和感がある
- 特定の指や手首の動きで引っかかりを感じることがある
- 朝起きた時に指や手首がこわばることがある
- 指を曲げ伸ばしする際に「カクッ」という小さな音がすることがある
- 手のひらや指の付け根を押すと痛みがある
- 長時間同じ作業をした後に指や手首がだるく感じる
- 物を掴む際に以前より力が入りにくいと感じることがある
- 指先や手のひらに痛みを感じることがある
- 手首を回したり手のひらを反らしたりする際にわずかな突っ張り感がある
- 安静にしていると症状が軽減するが使い始めると再び症状が現れる
腱鞘炎の検査・診断
患者さんの手や指、手首などを触診したり、動かしたりして状態を確認します。
理学検査
圧痛の確認
炎症が起きている腱鞘の部分を押して痛みがあるかを確認します。
痛みの再現
特定の動きをしてもらい、痛みが増強するかどうかを確認します。
フィンケルシュタインテスト (Finkelstein test)
ドケルバン病(手首の親指側の腱鞘炎)の診断に用いられることが多い検査です。親指を内側に握りこぶしを作り、手首を小指側に曲げることで、手首の親指側に強い痛みが生じるかどうかを確認します。
弾発現象の確認
ばね指の場合、指の曲げ伸ばしの際に引っかかりや「カクン」という音、跳ね返るような動き(弾発現象)があるかを確認します。
可動域の確認
指や手首の曲げ伸ばしの範囲が正常かどうかを確認することがあります。
画像検査
レントゲン検査

骨折や変形性関節症など、他の病気が痛みの原因になっていないかを確認するために行います。
超音波(エコー)検査
腱や腱鞘の状態、炎症の程度、腱鞘の肥厚などを確認するのに有用です。被ばくがないこと、リアルタイムに確認することができること、患者さんに動かしてもらいながら確認することができることが大きなメリットです。
MRI検査
より詳細な腱や腱鞘の状態、周囲の軟部組織の状態を確認するために行われることがあります。他の疾患との鑑別が難しい場合などに検討されます。
腱鞘炎は
レントゲンでわかる?
 腱鞘炎そのものはレントゲン検査では直接的に診断することはできません。
腱鞘炎そのものはレントゲン検査では直接的に診断することはできません。
レントゲンは主に骨の状態を評価するのに適した検査です。腱や腱鞘といった軟部組織の炎症や異常を直接的に映し出すことはできません。
腱鞘炎の診断における
レントゲン検査の意味
他の疾患との鑑別
手や手首の痛みの原因が、骨折、関節の変形、腫瘍など、他の病気ではないことを確認するために行われることがあります。特に、外傷の既往がある場合や、痛みの部位や性状から他の疾患が疑われる場合に検討されます。
関節の状態の評価
慢性的な腱鞘炎の場合、周囲の関節に変形などが生じているかどうかを確認することができます。
腱鞘炎の診断は、主に医師による問診と理学検査によって行われます。 触診で腱鞘の圧痛や腫れを確認したり、特定の動きで痛みが誘発されるかを調べたりすることで診断されることが多いです。
必要に応じて、腱や腱鞘の状態をより詳しく評価するために、超音波(エコー)検査やMRI検査などの画像検査が行われることがあります。特に超音波検査は、リアルタイムに腱や腱鞘の状態を観察できるため、腱鞘炎の診断に有用な場合が多くあります。
腱鞘炎の治療
腱鞘炎の治療は、炎症を抑え、痛みを軽減し運動機能を改善することを目的として行います。
治療法は、症状の程度や原因、患者さんの状態によって選択されます。
大きく分けて保存療法と手術療法があります。
保存療法
手術を行わない治療法で、初期の腱鞘炎や軽症~中等度の症状の場合に選択されます。
安静
原因となっている動作や作業をできる限り避けることが最も重要です。
手や指、手首を休ませることで、炎症の悪化を防ぎ、自然治癒を促します。
固定
サポーターや装具、テーピングなどを用いて患部を固定し、動きを制限することで、腱や腱鞘への負担を軽減します。
夜間のみ、または日中も装着するなど、症状に合わせて使用します。
薬物療法
外用薬
炎症や痛みを抑えるための湿布や塗り薬を使用します。
内服薬
痛みが強い場合には痛み止めやステロイドを処方することがあります。
注射療法
炎症が強い部位に、ステロイドや局所麻酔薬を注射することで、炎症を直接的に抑え、痛みを軽減します。
ただし、頻繁な注射は腱を弱める可能性があるため、1回で効かない場合、数回程度を限度として数週間の期間をおいて注射することがあります。
リハビリテーション

専用の機械を行い、血行を改善したり、炎症を抑えたりします。
痛みが軽減してきたら、徐々にストレッチや運動療法を行い、関節の可動域を広げ、周囲の筋肉を強化します。再発予防のための指導も行います。
手術療法
保存療法で十分な効果が得られない場合や、症状が慢性化・重症化している場合に検討し、患者さんが希望された場合、今までの経験を活かして適切な医療機関へ紹介いたします。
腱鞘切開術
狭くなった腱鞘を切開し、腱の通り道を広げる手術です。これにより、腱と腱鞘の摩擦が軽減され、痛みや障害が改善します。
手術の方法は、現在は様々な方法は行われています。
腱鞘炎に湿布を貼って良い?
腱鞘炎に湿布を貼ることは、症状の緩和に役立ちます。熱感や腫れ、痛みに対して、消炎鎮痛効果が期待できます。
手に湿布をはると剝がれやすいため、塗り薬を使用することも多いです。効果としては湿布同様に消炎鎮痛効果が期待できます。
塗り薬にはチューブタイプ、スティックタイプなどのタイプがあります。
慢性的な痛みや動きが気になる時期
温感湿布で血行を促し、筋肉をリラックスさせるのも一つの方法です。
炎症を抑え、痛みを和らげる効果は期待できますが、腱や腱鞘の修復を直接的に促すわけではありませんので初期症状の患者さんに適した治療法といえます。
当院では様々なタイプの薬の処方経験を持つ整形外科専門医が処方を行いますのでお気軽にご相談ください。
腱鞘炎は冷やす・温める
どちらが良い?
腱鞘炎の症状、状況、場所によって、冷やすのが良いか、温めるのが良いかが異なり一概には言えません。
急な痛みなどの炎症が強い時期
冷やすのが適しています。
炎症が起きてすぐの時期は、患部に熱感、腫れ、強い痛みがあることが多いです。
慢性的な痛みや動きが悪くなっている時期
温めるのが適している場合があります。
慢性期に入ると、炎症は落ち着いているものの、動かした時の痛みやこわばりが主な症状となります。
このような時期には、温めることで血行が促進され、筋肉や腱の柔軟性が高まり、痛みが軽減することがあります。
お風呂で温めるなども有効な場合があります。
どちらの場合も腱鞘炎だけではないことも多々あり、早めの整形外科受診が大事です。
当院ではどちらも診察可能ですので。お気軽にご相談ください。
腱鞘炎はマッサージを
したほうが良い?
腱鞘炎に対してマッサージが有効かどうかは、症状の段階や状態によって異なります。
初期の炎症が強い時期
この時期に強くマッサージをすると、炎症を悪化させる可能性があります。
炎症部位を直接刺激することは避け、安静にすることが重要です。
慢性的な痛みや可動域が悪くなっている時期
炎症が落ち着いている場合、適度なマッサージが血行を促進し、周囲の筋肉の緊張を和らげることで、症状の緩和に繋がる可能性があります。
ただし、炎症部位を直接強く揉むことは避けるべきです。
ご自身でマッサージを行う場合は、優しくさするようにする程度にしておいてください。
腱鞘炎の原因や状態は人それぞれ異なるため、自己判断でマッサージを行うことは、症状を悪化させる可能性があります。
お気軽に当院を受診いただくことで、適切な指導をうけていただくことができます。
腱鞘炎は何日くらいで治る?
腱鞘炎が治るまでの期間は、症状の程度や治療法、そして個人の状態によって大きく異なります。 一概に「何日くらい」と断言することは難しいです。
一般的には、以下の期間が目安とされています。
軽度の場合
安静にすることで数日から数週間で症状が改善することもあります。
中程度の場合
サポーターによる固定や外用薬などの保存療法を継続することで、数週間から数ヶ月で改善が見込めます。
重度の場合や慢性化している場合
保存療法に時間がかかったり、手術が必要になったりすることもあり、数ヶ月以上の治療期間を要することもあります。
患者さん自身で軽度、中等度、重度を判断することは非常に難しく、大事なのは、自己判断せずに整形外科受診を行うことです。
当院では、症状の程度に合わせて、固定、薬物療法、注射、リハビリテーションなどの適切な治療法を提供します。
腱鞘炎は放置しても治る?
腱鞘炎を放置しても、自然に治る可能性はありますが、時間がかかったり、症状が悪化したりすることがあるため、早めの治療をおすすめします。
軽度の腱鞘炎であれば、安静にすることで数週間程度の経過で自然に改善することもあります。しかし、多くの場合、日常生活で手や指を全く使わないというのは難しく、放置することで腱や腱鞘の炎症が慢性化し、痛みや機能障害が長引くことがあります。
腱鞘炎を放置することで
起こりうるリスク
痛みの慢性化
炎症が長引き、常に痛みを感じるようになることがあります。
機能障害の悪化
指が曲げ伸ばししにくくなったり、引っかかったりする「ばね指」の状態が悪化し、日常生活に支障をきたすことがあります。
可動域の制限
関節が硬くなり、動きが悪くなることがあります。
周囲の組織への影響
炎症が広がり、他の部位にも痛みが生じることがあります。
手術が必要になる可能性
症状が重症化すると、保存療法では改善が見込めず、手術が必要になる場合があります。
特に、ばね指を放置すると、指が完全に伸びなくなったり、曲がったままになったりするロッキング、拘縮という状態に進行する可能性があります。
したがって、「たかが腱鞘炎」と安易に考えずに、症状が現れたら早めに整形外科を受診し、適切な診断と治療を受けることが大切です。
固定、薬物療法、リハビリテーションなどの適切な治療を行うことで、早期の改善と慢性化の予防に繋がります。
当院へお気軽にご相談ください。
腱鞘炎は保険適用になる?
腱鞘炎の治療は一般的に保険適用になります。当院は保険医療機関ですので保険をもちいて診断から治療まで受けていただくことができます。
診察、レントゲン検査、湿布や内服薬の処方、注射、リハビリテーションなどの治療は、健康保険の適用対象となります。
お気軽に当院を受診ください。
ただし、以下のような場合は保険適用とならないことがあります。
- サポーターなどを購入する場合(一部保険適応の装具もあります。)
- 保険適応外の治療を希望される場合