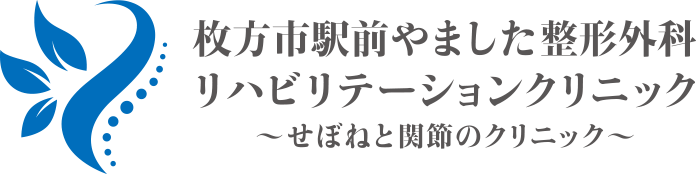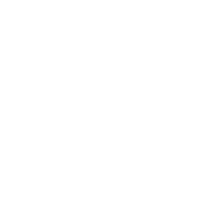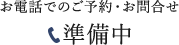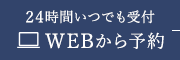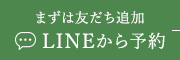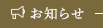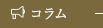捻挫・靱帯損傷とは
 捻挫は、関節が不自然にひねられることで、関節を安定させる役割を持つ「靭帯」や関節包、腱などが損傷する状態です。
捻挫は、関節が不自然にひねられることで、関節を安定させる役割を持つ「靭帯」や関節包、腱などが損傷する状態です。
特に靭帯が部分的に、あるいは完全に断裂したものを「靭帯損傷」と呼びます。
捻挫の多くは足首に発生しますが、手首や膝、指など、体の様々な関節で起こりえます。症状としては、痛み、腫れ、内出血、そして関節を動かしにくくなるといった機能障害が見られます。重症度によって、靭帯の伸びや部分断裂、完全断裂に分けられ、それぞれ治療法が異なります。
軽度なものでは安静やPRICE処置、装具などの治療で回復しますが、重度の場合には手術が必要となることもあります。
捻挫・靱帯損傷の原因
捻挫・靭帯損傷の主な原因は、スポーツ活動中の急な方向転換、ジャンプの着地失敗、転倒など、関節に強い衝撃や不自然なひねりが加わることです。
特に、足首の捻挫は、段差でのつまずきやハイヒール着用時。雨で滑って転ぶなど、日常生活の中でも起こりってしまうケガです。
関節が許容範囲を超えて動いてしまうと、関節を補強している靭帯や関節包、腱などが損傷します。
準備運動不足による筋肉の柔軟性の低下、筋力不足、過去の捻挫による靭帯の緩みなども、捻挫や靭帯損傷を起こしやすくする要因となる可能性があります。
これらの要因により、関節への負担が増大し、組織の損傷に至ってしまいます。
「足首が痛い」のは
捻挫・靱帯損傷?初期症状は?
- 足首を捻った(ぐねった)瞬間の急激な痛み
- 患部の腫れ(捻った直後から数時間以内、または徐々に)
- 内出血(足首を捻って青あざになることがある)
- 足首が痛くて動きにくい(曲げ伸ばしやひねる動作が困難)
- 体重をかけると痛む(歩行困難や、足を引きずるような歩き方になる)
- 患部を押すと強い痛みがある
- 関節の不安定感(ぐらつく感じ、ずれる感じ)
- 「ブチッ」という異音や感覚(アキレス腱断裂の可能性もあります)
- 安静にしていても痛む
捻挫・靱帯損傷の検査・診断
捻挫や靭帯損傷が疑われる場合、整形外科での診察が最も重要です。
自己判断はせず、整形外科専門医の診断を受けましょう。
捻挫・靭帯損傷の検査・診断における重要事項
診察の重要性
医師が症状を直接確認し、触診することで、痛む箇所や腫れの程度、関節の不安定性を詳細に評価します。これが診断の第一歩であり、非常に重要です。
レントゲンの重要性
捻挫や靭帯損傷の場合でも、骨折を合併しているケースがあります。そのため、大事なレントゲン検査を行い、骨折の有無を確認します。
靭帯そのものはX線には写りませんが、骨折の除外診断は必須です。
超音波(エコー)検査の活用
超音波検査は、靭帯の損傷程度や炎症の有無をリアルタイムで確認できるため、補助的に使用されることがあります。特に、靭帯の部分的な損傷や、軽度から中程度の損傷の診断に役立ちます。
MRI検査の必要性
痛みが続く場合や、より詳細な靭帯の損傷状態、軟骨や他の軟部組織の損傷を確認する必要がある場合には、MRI検査を検討することが多いです。MRIは靭帯の完全な断裂や複雑な損傷を高い精度で診断できます。
靱帯損傷は
レントゲンでわかる?

レントゲンは、X線という放射線を使って主に骨の状態を詳細に映し出すのに適しています。捻挫に合併した骨折など、骨に異常がないかを確認するために非常に有効な検査です。
しかし、靭帯は骨とは異なり、X線でははっきりと映らない「軟部組織」に分類されます。
そのため、靭帯が伸びたり、部分的に切れたり、完全に断裂していても、通常のレントゲン写真ではその損傷を直接確認することはできません。
ただし、骨折を伴っている場合や、靭帯の損傷によって関節の不安定性が生じ、骨の位置関係に変化が見られる場合は、レントゲン写真で間接的に靭帯損傷の可能性を示唆することがあります。
より詳しい靭帯の損傷具合を評価するには、超音波(エコー)検査やMRI検査といった、軟部組織の描出に優れた検査が必要となります。
状況に合わせ、段階的な検査を要することが多いケガの一つです。
捻挫・靱帯損傷の治療
捻挫・靭帯損傷の治療は、損傷の程度によって異なります。
大きく分けて「保存療法」と「手術療法」があります。
まず、受傷直後にはPRICE処置(保護・安静・冷却・圧迫・挙上)が基本です。これは、腫れや痛みを抑え、損傷の悪化を防ぐための応急処置です。
診断の結果、軽度な捻挫の場合は、サポーターなどを用いた固定で関節を安静に保ち、自然治癒を促します。痛みを伴うため、痛み止めや湿布などの薬物療法を併用する場合が多いです。
中等度から重度な靭帯損傷の場合や、関節の不安定性が著しい場合には、ギプスなどによる、より強固な固定が必要となることがあります。
また、固定期間後や痛みが落ち着いてきたら、リハビリテーションを開始します。
関節の可動域を改善し、筋力を回復させることで、再発予防と機能回復を目指します。
また再発予防も非常に重要なリハビリテーションの一つです。
まれに靭帯が完全に断裂している場合や、保存療法では改善が見られない慢性的な不安定症の場合には、靭帯再建術などの手術が検討されます。
捻挫は何日で治る?
捻挫が治るまでの期間は、その重症度によって大きく異なります。
軽度の捻挫
靭帯がわずかに伸びた程度ので、痛みや腫れも比較的軽いです。数日から1週間程度で日常生活に戻れることが多いですが、完全に痛みがなくなるまでは数週間かかることもあります。
中度の捻挫
靭帯の一部が断裂したもので、痛みや腫れが強く、内出血を伴うこともあります。治癒には数週間から1-2ヶ月程度かかることが一般的です。添え木、ギプスなどの固定が必要になる場合も多くなります。
重度の捻挫
靭帯が完全に断裂したもので、強い痛みと腫れ、著しい不安定感を伴います。完治までには数ヶ月かかることもあり、手術が必要となる場合もあります。
重要なのは、捻挫だと思っても、まれに骨折が隠れていたり、はじめは大丈夫でも後になって骨折が判明したりすることもあります。
初期だけでなく継続的な診察と適切な治療が非常に重要である点です。
症状が改善しない場合は、必ず再受診してください。
捻挫は冷やす・温める
どちらが良い?
 捻挫の急性期、つまり受傷直後から数日間は、冷やすのが良いです。
捻挫の急性期、つまり受傷直後から数日間は、冷やすのが良いです。
捻挫すると、損傷した組織で炎症が起こり、痛みや腫れ、熱感が生じます。冷やすことで、これらの炎症反応を軽減する効果があります。
これにより、痛みを和らげ、腫れの広がりを和らげることができます。氷嚢、アイスパックなどをタオルで包み、15~20分程度患部に当て、患部を冷やし、休憩を挟んで繰り返すのが良いでしょう。詳しくは診察の際にお知らせします。
一方、受傷から数日経ち、炎症が落ち着いてきた慢性期(痛みや腫れ、熱感が引いてきた頃)には、温めることが有効になる場合があります。
温めることで血行が促進され、組織の回復を助ける効果が期待できます。ただし、まだ炎症が残っている段階で温めると、かえって症状を悪化させる可能性があるので、タイミングには注意が必要です。
タイミングは整形外科受診時に適切に切り替えていくことが重要です。
基本的には、受傷直後は冷やす、が原則と覚えておきましょう。
捻挫でやってはいけないこと
患部を無理に動かすこと
損傷した靭帯や組織に更なる負担をかけ、悪化させてしまう可能性があります。
温めること
受傷直後の急性期に温めると、血管が拡張して炎症や腫れ、内出血が悪化する恐れがあります。
飲酒
アルコールには血管を広げる作用があり、炎症や腫れを悪化させる可能性があります。許可が出るまでお酒は控えてください。
マッサージ
炎症が強い急性期にマッサージを行うと、組織の損傷を広げたり、炎症を悪化させたりする可能性があります。
入浴
湯船に浸かると体が温まり、血行が促進されて炎症や腫れが増す恐れがあります。許可がでるまでシャワーのみにしておいてください。
自己判断で放置すること
軽度だと思っても、実は骨折を伴っていたり、重度の靭帯損傷であったりする可能性があり、適切な治療が遅れると回復が遅れたり、後遺症が残ったりするリスクがあります。整形外科を受診することをお勧めします。
痛みを我慢して運動を続けること
完全に治りきっていない状態で無理に運動を再開すると、再発や慢性化の原因になります。