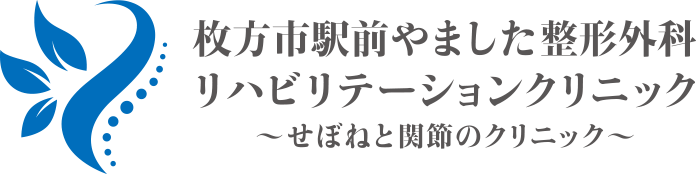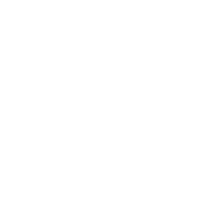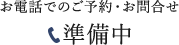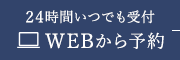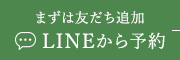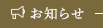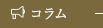足底筋膜炎とは
 足底筋膜炎とは、足の裏にある腱組織である足底筋膜に炎症が起こり、痛みが生じる疾患です。足底筋膜は、かかとから足の指の付け根まで伸びており、土踏まずを支え、歩行時の衝撃を吸収する役割を担っています。主な症状としては、起床時や長時間座った後の最初の数歩でかかとや土踏まずに強い痛みを感じることが挙げられます。歩いているうちに痛みが軽減することもありますが、運動後や長時間の立ち仕事などで再び痛みが増強することがあります。
足底筋膜炎とは、足の裏にある腱組織である足底筋膜に炎症が起こり、痛みが生じる疾患です。足底筋膜は、かかとから足の指の付け根まで伸びており、土踏まずを支え、歩行時の衝撃を吸収する役割を担っています。主な症状としては、起床時や長時間座った後の最初の数歩でかかとや土踏まずに強い痛みを感じることが挙げられます。歩いているうちに痛みが軽減することもありますが、運動後や長時間の立ち仕事などで再び痛みが増強することがあります。
足底筋膜炎の原因
足底筋膜炎の主な原因は、足の裏にある腱組織である足底筋膜への過度な負荷と、それによる微細な損傷の蓄積です。具体的には、以下のような要因が複雑に絡み合って発症することが多いと考えられています。
環境因子
使いすぎ(オーバーユース)は非常に一般的な原因です。長距離のランニングやジャンプを伴うスポーツ、長時間の立ち仕事など、足に繰り返し強い衝撃が加わることで、足底筋膜に負担がかかり炎症を引き起こします。特に、運動習慣のない方が急に激しい運動を始めたり、運動量を急激に増やしたりした場合に起こりやすいです。
加齢
年齢を重ねるにつれて、足底筋膜の柔軟性や弾力性が低下し、衝撃を吸収する能力が弱まります。これにより、日常的な動作でも足底筋膜が損傷しやすくなります。
身体的因子
身体的因子として足の構造的な問題も影響します。例えば、扁平足(土踏まずが低い)やハイアーチ(土踏まずが高い)といった足のアーチの異常があると、足底筋膜にかかる負担が偏りやすくなります。扁平足の場合は、足底筋膜が常に引き伸ばされた状態になりやすく、ハイアーチの場合は、特定の部位に過度な負荷がかかりやすくなります。
不適切な靴
不適切な靴の使用も要因の一つとなります。クッション性の低い靴や底の薄い靴、ヒールの高い靴などは、足への衝撃を十分に吸収できず、足底筋膜に直接的な負担をかけます。足に合わない靴も同様に、特定の部位に負担を集中させる可能性があります。
体重増加
体重の増加も足底筋膜への負担を増大させる要因となります。
アキレス腱の柔軟性低下
アキレス腱の柔軟性低下も間接的な原因となり得ます。アキレス腱が硬いと、足関節の可動域が制限され、歩行時に足底筋膜が過度に引っ張られやすくなるため、負担が増加します。
これらの要因が単独で、あるいは複合的に作用することで、足底筋膜に炎症が生じ、足底筋膜炎を発症すると考えられています。
ストレスで
足底筋膜炎になる?
ストレスが直接的な原因として足底筋膜炎を引き起こすという医学的根拠は現在のところありません。
しかし、間接的にストレスが足底筋膜炎の発症や悪化に関与する可能性は考えられます。
過度なストレスは、自律神経の乱れを引き起こし、影響を体に及ぼすことがあります。
筋肉の緊張
ストレスにより全身の筋肉が緊張しやすくなります。足の筋肉やアキレス腱が緊張することで、足底筋膜にかかる負担が増加する可能性があります。
血行不良
ストレスは血管を収縮させ、血行を悪くすることがあります。足底筋膜の血行が悪くなると、組織の修復が遅れ、炎症が悪化する可能性があります。
痛覚過敏
ストレスが慢性化すると、痛覚が過敏になることがあります。これにより、軽微な足底筋膜の炎症でも強い痛みとして感じやすくなる場合があります。
生活習慣の変化
ストレスにより、運動不足になったり、不健康な食生活になったりすることがあります。これらが間接的に足の健康を損ない、足底筋膜炎のリスクを高める可能性があります。
また、ストレスを感じやすい性格の人は、痛みに過敏であったり、痛みを我慢しすぎたりする傾向があるかもしれません。これにより、足底筋膜炎の初期症状を見過ごしたり、適切な休息を取らなかったりすることで、症状が悪化する可能性も考えられます。
喫煙習慣
ストレスがかかると喫煙する人もおられ、喫煙によって足底の血流が悪くなり、結果として炎症の改善が遅延することがあります。
したがって、ストレスそのものが直接的な原因ではありませんが、ストレスが体の状態や生活習慣に影響を与え、結果として足底筋膜炎の発症や悪化を招く可能性は否定できません。
足底筋膜炎になりやすい人
- ハードな運動習慣のある人
- 急な運動やトレーニングを始めたばかりの人
- 長時間の立ち仕事をする人
- ヒールの高い靴や底の薄い靴をよく履く人
- 扁平足
- アキレス腱の柔軟性が低い人
- 体重過多・肥満の人
- 加齢
- 合わない靴を使用している人
- 過去に足の怪我をしたことがある人
足底筋膜炎の症状(初期症状)
足底筋膜炎の初期症状として最も多くみられるのは、起床時や長時間座った後、動き始めの一歩を踏み出す際の、かかと内側から土踏まずにかけての鋭い痛みです。
具体的には、以下のような症状が現れることが多いです。
起床時の一歩目の激痛
寝ている間に足底筋膜が収縮し、再び体重がかかることで急激に引き伸ばされ、強い痛みを感じます。
立ち上がりや歩き始めの痛み
長時間座っていた後など、足を動かしていなかった状態から立ち上がったり、歩き始めたりする際に、同様の痛みが生じます。
動いているうちに痛みが軽減する
しばらく歩いたり、足を動かしているうちに、足底筋膜が徐々に伸びてくるため、痛みが和らぐことがあります。
安静にしていると痛みは少ない
休んでいる間は、ほとんど痛みを感じないことが多いです。
局所的な圧痛
かかとの骨の前内側(土踏まずとの境目あたり)を押すと、強い痛みを感じることがあります。
これらの初期症状は、放置すると慢性化し、日中や運動時にも痛みが続くようになることがあります。また、痛みをかばうことで、足首や膝、腰など他の部位に負担がかかり、新たな痛みが生じる可能性もあります。
もし、上記のような初期症状に気づいたら、悪化する前に整形外科受診をお勧めします。
当院では足底腱膜炎の診断、治療を行っております。お気軽に受診ください。
更年期にかかとが痛くなるのは足底筋膜炎?
更年期にかかとの痛みを感じる場合、足底筋膜炎の可能性は十分に考えられます。実際、更年期は足底筋膜炎を発症しやすい時期と言われています。
その理由としては、更年期に伴う女性ホルモン(エストロゲン)の減少が、以下のように足底筋膜に影響を与える可能性があるからです。
組織の柔軟性低下
エストロゲンは、腱や靭帯などの組織の柔軟性を保つ働きにも関わっています。減少により、足底筋膜が硬くなり、些細な負荷でも炎症を起こしやすくなります。
筋力低下
全身の筋力低下も起こりやすくなり、足の裏の筋肉や腱を支える力が弱まることで、足底筋膜に負担がかかりやすくなります。
骨密度の低下
骨粗鬆症のリスクが高まり、かかとの骨に微細な損傷が起こりやすくなることも、痛みの原因となることがあります。
体重の変化
更年期には体重が増加しやすい方もおり、足底筋膜への負担が増加します。
足底筋膜炎の典型的な初期症状としては、朝起きて最初の一歩を踏み出す際に、かかとや土踏まずに強い痛みを感じることが挙げられます。歩いているうちに痛みが軽減することもありますが、再び悪化することもあります。
ただし、更年期にかかとの痛みが生じる原因は、足底筋膜炎だけとは限りません。他の疾患や要因も考えられます。
自己判断せずに、まずは整形外科を受診して、正確な診断を受けることが非常に重要です。
当院では足底腱膜炎はもちろん、骨密度検査、血管年齢の診察、検査を行うことができます。お気軽に受診ください。
足底筋膜炎の検査・診断
足底筋膜炎の診断は、問診と身体診察が中心となります。まず、いつから、どのような時に、どの部位に痛みがあるのかを問診します。
特に、朝起きてからの第一歩や、長時間座った後の歩き始めに痛みが強いという特徴的な症状は診断の重要な手がかりとなります。
次に、足裏、特に踵の骨に足底筋膜が付着する部分を医師が触診し、圧痛の有無を確認します。足の指を反らすことで痛みが誘発されるかどうかも確認します。
画像検査としては、X線検査で踵の骨に「骨棘(こつきょく)」と呼ばれる骨のトゲがないかを確認することがあります。これは必ずしも痛みと関連するわけではありませんが、長期にわたる炎症の兆候となることがあります。より詳細な状態を確認するために、超音波(エコー)検査やMRI検査を行うことがあります。これらは足底筋膜の肥厚や炎症の程度、損傷の有無などを評価するのに役立ち、他の疾患との鑑別にも用いられます。MRIは当院に持ち合わせていませんので提携医療機関へ当院で手配し紹介させていただくことになります。
足底筋膜炎は
レントゲンでわかる?

レントゲン検査は、足底筋膜炎そのものを直接的に診断することはできません。なぜなら、足底筋膜は腱組織であり、レントゲンには骨のように写らないため、炎症の状態を捉えることができないからです。
しかし、足底筋膜炎の診断において、レントゲン検査は重要な役割を果たします。その理由は以下の通りです。
踵骨棘(しょうこつきょく、かかとの骨のとげ)の確認
足底筋膜が長期間にわたって踵の骨に付着する部分を引っ張る力が加わることで、骨が反応してトゲのような突起を形成することがあります。レントゲン検査でこの骨棘の有無を確認することが、足底筋膜炎の診断の参考になることがあります。
他の疾患との鑑別
レントゲン検査は、疲労骨折など、かかとの痛みを引き起こす可能性のある他の疾患を除外するために役立ちます。これらの疾患は骨に異常が見られるため、レントゲンで確認できる場合がありますが微細な骨折などはCT検査が必要になる場合があります。
足の骨の構造の評価
扁平足やハイアーチなど、足の骨の構造的な異常が足底筋膜炎のリスクを高めることがあります。レントゲン検査でこれらの構造的な特徴を確認することがあります。
したがって、足底筋膜炎の診断は、患者さんの症状、整形外科による診察が最も重要です。レントゲン検査は、これらの情報と合わせて、診断の補助や他の疾患の除外のために行われます。
必要に応じて、超音波検査やMRI検査などの画像検査が行われることもあります。超音波検査では、足底筋膜の肥厚や炎症、断裂などを確認でき、MRI検査では、より詳細な軟部組織の状態や他の病変の有無を確認することができます。
足底筋膜炎の治療
多くの場合、手術ではなく、保存療法が中心となります。当院では、症状の程度や患者さんの状態に合わせて、患者さんと相談しながら個別に判断します。
保存療法
安静
痛みが強い時期には、運動や長時間の立ち仕事を避け、足への負担を減らすことが重要です。
アイシング
炎症を抑えるために、痛む部分を冷やします。
ストレッチ
足底筋膜やアキレス腱の柔軟性を高めるためのストレッチを行います。医師や理学療法士の指導のもと、正しい方法で行うことが大切です。
装具療法(インソール)
土踏まずをサポートするインソールを使用することで、足底筋膜への負担を軽減します。患者さんの足の形に合わせて作成する医療用のインソールもあります。
薬物療法
内服薬
痛みや炎症を抑えるための非ステロイド性消炎鎮痛薬(NSAIDs)などが処方されます。
外用薬
湿布や塗り薬などの外用薬が処方されることもあります。
注射
痛みが非常に強い場合や、他の治療で効果が見られない場合に、局所麻酔薬やステロイド薬を注射することがあります。ただし、ステロイド注射は繰り返すと副作用のリスクがあるため、慎重に行われます。
リハビリテーション
(理学療法)
痛みが軽減してきたら、足底筋膜や周囲の筋肉の強化、柔軟性改善、正しい歩き方の指導などが行われます。物理療法(電気治療、超音波治療など)を併用することもあります。
体外衝撃波療法
保存療法で効果が得られない難治性の足底筋膜炎に対して、体外から衝撃波を照射する治療法です。日本では、一定の条件を満たせば保険適用となります。痛みの軽減や組織の修復を促す効果が期待されています。
手術療法
保存療法を数ヶ月以上行っても症状が改善しない、ごくまれなケースで手術が検討されることがあります。手術の方法としては、足底筋膜の一部を切離したり、神経の圧迫を解除したりするものがあります。この場合、適切な医療機関へ紹介いたします。
足底筋膜炎は
インソール治療で治る?
 足底筋膜炎の治療において、インソールは非常に重要な役割を果たし、症状の改善や緩和に大きく貢献します。
足底筋膜炎の治療において、インソールは非常に重要な役割を果たし、症状の改善や緩和に大きく貢献します。
しかし、「インソール治療だけで完全に治るのか?」という点については、一概には言えません。
インソールが足底筋膜炎に有効な理由は以下の通りです。
土踏まずのサポート
足のアーチ(土踏まず)を適切にサポートすることで、足底筋膜にかかる過度な負担を軽減します。これにより、炎症の悪化を防ぎ、組織の回復を促します。
衝撃の吸収
クッション性のある素材を使用したインソールは、歩行や運動時の衝撃を吸収し、足底筋膜への負担を和らげます。
痛みの軽減
上記のメカニズムにより、歩行時の痛みを軽減する効果が期待できます。
しかし、足底筋膜炎の原因は一つではなく、使いすぎ、加齢、足の変形、不適切な靴、体重増加、アキレス腱の柔軟性低下など、様々な要因が複雑に絡み合って発症することが多いです。
そのため、インソール治療だけで完全に治癒するケースもあれば、他の治療法と併用する必要がある場合もあります。
実際多くの患者さんがインソール治療を含めたオーダーメイドな治療で大幅な改善がみられます。
当院ではインソール外来を設けており、整形外科医、装具士による専門的なインソールを提供できます。
大事なことは
- 適切なインソールを選ぶこと: 足の形状に合わせて作成する医療用のインソールがより効果的な場合があります。当院受診し、適切な装具について整形外科医、義肢装具士に相談して、自分に合ったインソールを選ぶことが重要です。
- 他の保存療法と併用すること: 安静、アイシング、ストレッチ、薬物療法、リハビリテーションなど、他の治療法と組み合わせることで、より高い治療効果が期待できます。
- 生活習慣を見直すこと: 靴の見直し、体重管理、運動量の調整など、足底筋膜に負担をかけない生活習慣を心がけることが大切です。
上記の治療は当院にて提供することができます。お気軽にご相談ください。
足底筋膜炎は痩せたら治る?
上記の原因のところに記述したました通り、体重が増加すると、足底筋膜炎の痛みを悪化させる可能性があります。そのため、体重を減らすことは、足底筋膜炎の症状を軽減する上で有効な手段の一つと言えます。
しかし、「痩せたら完全に治る」と断言することは難しいです。その理由は以下の通りです。
体重以外の原因
足底筋膜炎は、使いすぎ、加齢、足の骨格の異常(扁平足・ハイアーチ)、不適切な靴、アキレス腱の柔軟性低下など、体重以外の様々な要因によっても発症します。これらの原因が解消されない限り、体重が減っても症状が残る可能性があります。
炎症の慢性化
長期間にわたって炎症が続いている場合、体重が減ったとしても、組織の修復には時間がかかることがあります。
他の治療との併用
足底筋膜炎の改善には、体重管理だけでなく、適切なストレッチ、インソール、安静、薬物療法などの総合的な治療が重要です。
体重減少が足底筋膜炎に良い影響を与えるのは確かです。 足への負担が減ることで、症状の緩和や改善を促すことが期待できます。しかし、それだけで完全に治癒するとは限らず、他の治療法と並行して取り組むことが大切です。
当院ではオーダーメイドな治療を提供しています、お気軽にご相談ください。
足底筋膜炎は自然に治る?
足底筋膜炎は、足の裏の腱組織に炎症が起きることで痛みを引き起こす疾患です。軽症であれば、安静にしたり、ストレッチやインソールなどのセルフケアを行うことで、数週間から数ヶ月で自然に治ることもあります。
しかし、痛みが3週間以上続く場合や、悪化している場合は、自己判断せずに整形外科を受診することが非常に重要です。なぜなら、放置すると慢性化し、治療が長引く可能性があるだけでなく、疲労骨折など他の疾患が隠れている場合もあるからです。整形外科では、正確な診断のもと、薬物療法や物理療法、リハビリテーション、理学療法士によるストレッチ指導、装具氏によるインソール作成など、症状に合わせた適切な治療を受けることができます。早期の受診が、より早い回復と再発防止につながります。
足底筋膜炎で
やってはいけないことは?
足底筋膜炎の症状を悪化させたり、治癒を遅らせたりする可能性のある「やってはいけないこと」がいくつかあります。以下に主なものを挙げます。
- 痛みを我慢して無理な運動や活動を続けること
- 急な運動やストレッチ
- クッション性の低い靴やヒールの高い靴を履き続けること
- 裸足やスリッパで過ごすこと
- 長時間の立ちっぱなし
- 患部を温めること(急性期): 炎症が強く、痛みが出始めたばかりの急性期に温めると、炎症を助長してしまう可能性があります。痛みが強い時期はアイシングで冷やしましょう。慢性期で血行を促進したい場合は、温めることが有効な場合もありますが、自己判断せず医師や理学療法士に相談しましょう。
- 自己流の間違ったマッサージ: 誤った方法でのマッサージは、かえって組織を痛めてしまうことがあります。
- 痛みを放置して治療をしないこと