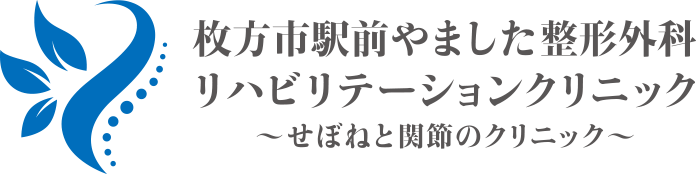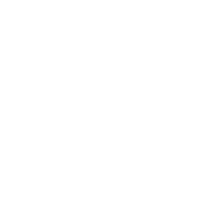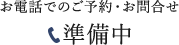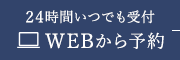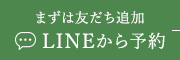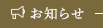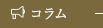骨粗鬆症とは
骨密度低下・かかとのスクリーニングを指摘された方へ

骨粗鬆症(こつそしょうしょう)とは、骨の密度や質が低下し、骨がもろくなって折れやすくなる病気です。特に高齢者や閉経後の女性に多く見られます。骨は常に作っては壊す、という新陳代謝を繰り返しており、古い骨が壊され新しい骨が作られることで維持されていますが、加齢やホルモンバランスの変化、栄養不足、運動不足などが原因でこのバランスが崩れると、骨の量が減少して骨粗鬆症になります。初期には自覚症状がほとんどないため、気づかないうちに進行し、軽い転倒やくしゃみなどでも骨折する危険性があります。骨折は特に背骨、手首、大腿骨の付け根などに起こりやすく、生活の質を大きく損なう原因になります。
2025年には骨粗鬆症ガイドライン(標準的な考え、治療が示されたもの)が刷新され、さらに骨粗鬆症の重要性を意識内容となっています。
「骨密度低下で要精密検査」「かかとの骨の検査で異常を指摘された」「骨密度が下がっています」「骨塩定量低下状態」などは精密検査が必要となります。
日本骨粗鬆症学会専門医とは
当院 院長は日本骨粗鬆症学会認定専門医です。
日本骨粗鬆症学会専門医は、骨粗鬆症の診断・治療・予防に関する高度な専門知識と臨床経験を有する医師に対して、日本骨粗鬆症学会が認定する資格です。この専門医制度は、骨粗鬆症の医療水準を向上させ、患者さんに質の高い医療を提供することを目的としています。
認定を受けるためには、医師免許を有し、骨粗鬆症の臨床に関わる経験を積み、研修を受けることを必須としています。
また、過去3年以内に日本骨粗鬆症学会の学術集会に参加し、所定の発表・論文や研修・講習を受講することが必須です。
さらに、学会が定める資格要件を満たし、必要な書類を提出して厳しい審査を受けることで、初めて専門医として認定されます。
当院では、上記のように、骨粗鬆症に関して興味を持ち、治療の重要性を認識し、訓練を積んだ医師が診療を行います。
気になることがあればお気軽に受診し、ご相談ください。
骨粗鬆症の原因
骨粗鬆症の原因は多岐にわたりますが、主に骨の形成と吸収のバランスが崩れることが発症の根本にあります。
一番多いのが原発性骨粗鬆症といわれる、加齢によって骨の新陳代謝のバランスが崩れ、骨量が減少することが最も一般的な原因です。
特に閉経後の女性では、エストロゲンという女性ホルモンの分泌が急激に減少するため、骨の吸収が進みやすくなります。
また、カルシウムやビタミンDの不足、運動不足、喫煙、過度の飲酒も骨密度の低下を招く要因です。
2次性骨粗鬆症と言われる、遺伝的な体質や、糖尿病、甲状腺機能亢進症、ステロイド薬の長期使用など、特定の疾患や薬剤も発症リスクを高めます。
骨粗鬆症になりやすい人
(特徴)
 骨粗鬆症になりやすい人には、体質や生活習慣、ライフスタイルに特徴があります。
骨粗鬆症になりやすい人には、体質や生活習慣、ライフスタイルに特徴があります。
まず、女性は男性に比べて骨量が少ないうえ、閉経によるホルモンの変化で発症リスクが高くなります。特にやせ型で筋肉量が少ない人は、骨にかかる負荷が少ないため骨が弱くなりやすい傾向にあります。
また、身長が急に縮んだり、背中や腰が曲がってきたと感じる人も注意が必要です。姿勢の悪さや長時間同じ姿勢でいることが多い人、デスクワーク中心の生活を送っている人もリスクが高くなります。
日に当たる機会が不足すると体内のビタミンDが不足するため、インドア志向で外出の少ない人も骨の代謝を損ないやすいです。さらに、成長期に十分な栄養と運動をしてこなかった若年者も、将来的に骨粗鬆症のリスクを抱えることになります。
男性は70歳以上、女性は65歳以上で骨密度検査を受けることを推奨されています。
また、喫煙歴がある、長期の飲酒習慣がある、ステロイド治療中、低体重、骨折歴があるなどのリスク因子を持つ場合は、50歳以降からの早期検査が望ましいとされています。
骨密度と体重の関係(痩せは骨密度になりやすい?)
痩せている人は骨密度が低くなりやすく、骨粗鬆症のリスクが高くなることが多くの研究で明らかになっています。以下にその理由を詳しく説明します。
骨密度と体重の関係
骨密度(骨の強さを示す指標)は、体重や筋肉量と密接に関係しています。体重がある程度ある人は、骨にかかる負荷(重み)が大きく、それが刺激となって骨が強く保たれます。逆に、痩せていて体重が軽い人は骨への刺激が少なく、骨が弱くなりやすいのです。
また、筋肉量が少ないことも骨密度の低下につながります。筋肉の収縮によって骨に力が加わることで、骨は強く保たれる仕組みがあるため、筋肉が少ないと骨への刺激も減り、骨量が減少しやすくなります。
痩せ型の人の特徴とリスク
BMIが低い(身長に対して体重が低い)人は、骨粗鬆症になりやすい傾向があります。
痩せている女性、特に月経不順や無月経のある人は、エストロゲン(骨を守る女性ホルモン)の分泌が減り、骨密度がさらに低下しやすいです。
過度なダイエットや拒食症の既往がある人も、栄養不足によって骨の形成が妨げられ、骨密度が著しく低下することがあります。
予防と対策
痩せている人が骨密度を保つには、以下のような対策が重要です
- バランスの良い食事(特にカルシウム・ビタミンD・たんぱく質の摂取)
- 筋肉をつけるための運動(特に負荷のかかる運動や筋トレ)
- 適正体重の維持(無理な減量は避ける)
- 日光浴によるビタミンDの生成
- 早めの骨密度検査
骨粗鬆症の初期症状
骨粗鬆症は初期には自覚症状が少ない病気ですが、進行するにつれて以下のような初期症状が見られることがあります。
- 軽い動作やくしゃみで骨折する(特に背骨・手首・肋骨など)
- 身長が以前より縮んだ気がする
- 背中や腰に慢性的な痛みがある
- 背中が丸くなる(円背)
- 長時間立っているのがつらい
- 些細な転倒でも骨折を起こしやすい
- 背中や腰を押すと痛みを感じる
- 姿勢の変化や歩行時に違和感を覚える
これらの症状がある場合は、骨密度検査などで早めに状態を確認することが重要です。
当院へお気軽にご相談ください。
骨粗鬆症の検査・診断
まずは自宅でできる検査として身長測定(過去より縮んでいないか)、身長の縮みは、骨粗鬆症の重要な初期サインです。特に以下のような変化が見られる場合には注意が必要です。
- 若い頃と比べて2cm以上の身長低下
- 背中が曲がってきた、猫背になったと感じる
- 頻繁に腰痛や背中の違和感がある
これらの変化は、背骨の圧迫骨折がすでに起こっている可能性があり、無症状であっても骨粗鬆症が進行していることがあります。そのため、定期的な身長測定は、ご自宅でできる簡単ながら有効なスクリーニング手段です。
FRAX®(Fracture Risk Assessment Tool) は、世界保健機関(WHO)が開発した、今後10年間に大腿骨や脊椎などの骨折を起こすリスクを予測するためのツールです。骨密度が分からない場合でも使えるのが特徴です。
FRAX®により、リスクが一定以上と判定された場合には、骨密度測定(DEXA)などの精密検査をすすめられます。
骨密度測定(BMD検査)
最も基本的かつ重要な検査で、骨の密度(強さ)を数値で評価します。

DEXA法
(二重エネルギーX線吸収測定法)
腰椎や大腿骨などにX線を照射して骨密度を測定。最も信頼性が高く、重要な検査です。
MD法(超音波法)
かかとの骨などに超音波を当てて骨の状態を測定。簡便で被爆もなく、健康診断、ドッグなどでスクリーニング検査(病気の可能性を早期に発見するために行う簡易的な検査)として利用され、診断目的に行う検査ではありません。
X線検査(レントゲン)
背骨などの骨折の有無を確認するために行います。
すでに骨折している場合、骨粗鬆症がかなり進行している可能性があります。
血液・尿検査
骨の代謝状態を調べ、骨の吸収や形成のバランスを把握します。以下の項目などがチェックされます。
- 血中カルシウム・リン
- 骨代謝マーカー(TRACP-5b、P1NP など)
- ビタミンDの血中濃度
そのほかの項目も同時に検査し、お薬の選択などの判断材料となります。
骨粗鬆症の治療
薬物療法
骨の代謝のバランスが崩れている状態を整えることで骨密度の治療を行うお薬です。
骨の形成を促進したり、骨の吸収を抑えたりする薬を使用します。
代表的なお薬を以下に記します。
骨吸収抑制薬
(骨を壊す働きを抑える薬)
- ビスホスホネート製剤
(アレンドロネート、リセドロネートなど)
昔からよく使われているお薬です。骨の破壊を抑制することで骨代謝の是正を図ります。
選択的エストロゲン受容体モジュレーター(SERM)
閉経後女性で比較的若年者に用いるお薬で、女性ホルモンに似た作用で骨を守る(ラロキシフェンなど)。
デノスマブ(注射薬)
骨吸収を抑える抗体注射製剤。半年に1回の注射で治療を行います。飲み薬を併用する場合もあります。
骨形成促進薬(骨を作る薬)
- テリパラチド(副甲状腺ホルモン製剤)
骨形成を促し、骨代謝回転を上昇させる注射薬です。
ロモソズマブ
(抗スクレロスチン抗体)
骨吸収抑制と骨形成促進の両方の作用を持つ新しい注射薬です。
- 補助的治療薬
- カルシウム製剤
- ビタミンD製剤
(活性型含む) - ビタミンK2製剤
上記のお薬の他にも種類があります。
当院では骨粗鬆症専門医が生活に合わせたお薬を提案いたします。
持ち物はお薬手帳です。お気軽にご相談ください。
骨密度を増やす食べ物は?
1. カルシウムを多く含む食品
- 牛乳・ヨーグルト・チーズなどの乳製品
- 小魚(ししゃも、いわしの丸干し)
- 大豆製品(豆腐、納豆)
- 青菜(小松菜、チンゲンサイ)
- ごま、ひじき、干しエビ
2. ビタミンD
カルシウムの吸収を助け、骨への沈着を促す成分です。
- 鮭、サンマ、イワシなどの魚
- きくらげ、干ししいたけ
- 卵黄
3. ビタミンK
カルシウムを骨に定着させ、骨の質を高める成分です。
多く含む食品
- 納豆
- 緑黄色野菜(ほうれん草、ブロッコリーなど)
- 海藻類
4. たんぱく質
- 肉類、魚類、卵
- 大豆製品(豆腐、納豆、豆乳)
- 乳製品
5. マグネシウム・亜鉛
骨の代謝をサポートするミネラル成分です。
Mgが多く含む食品
- アーモンド、カシューナッツ
- 海藻類(ひじき、わかめ)
- 玄米
亜鉛が多い食品
- 牛肉、レバー
- 牡蠣
- 大豆製品
食事のポイント
- カルシウムだけでなく、吸収・定着に関わる栄養素もバランスよくとる
- 加工食品や過剰な塩分はカルシウムの排出を促進するため注意
- アルコール・カフェインの過剰摂取も控えめに
コーヒーは
骨密度に影響する?
カフェインと骨密度の関係
 コーヒーに含まれるカフェインには、以下のような骨への影響が指摘されています。
コーヒーに含まれるカフェインには、以下のような骨への影響が指摘されています。
カルシウムの排出を促進
カフェインは腎臓からのカルシウム排出を増加させるため、体内のカルシウムが不足しやすくなることがあります。
骨密度低下のリスク
(特に高齢女性)
大量にコーヒーを飲む人では、骨密度がやや低い傾向がみられたという研究もあります。
特に閉経後の女性や、カルシウム摂取量が不足している人では注意が必要です。
カフェインの摂取が骨密度に与える影響は、摂取量や他の栄養バランスによって大きく変わります。
わからないことがあればお気軽に当院へ受診、ご相談ください。
歩くと骨密度は上がる?
 歩くこと(ウォーキング)は骨密度の維持・向上に効果があります。特に中高年以降の骨粗鬆症予防として、継続的な歩行運動は非常に重要です。
歩くこと(ウォーキング)は骨密度の維持・向上に効果があります。特に中高年以降の骨粗鬆症予防として、継続的な歩行運動は非常に重要です。
なぜ歩くと骨密度が上がるのか?
骨は「負荷(衝撃や重力)」がかかることで、骨を強くしようとする働きが活性化します。
- 時間は1日20~30分以上
- 頻度は、週3~5回以上が理想
- 歩く速度は、会話はできるが息が少し弾む程度
- その他 正しい姿勢、やや早歩きが効果的
骨密度への効果が期待できる人
- 運動習慣のなかった人
- 閉経後の女性
- 加齢によって筋力や骨量が低下してきた人
- デスクワーク中心で活動量が少ない人
こういった人が歩く習慣を取り入れると、骨密度の維持や改善につながる可能性が高いです。
歩くことは、骨に適度な刺激を与えて骨密度を高める自然で安全な方法です。特別な器具もいらず、今日からでも始められます。
骨を守るために、日常に「歩く習慣」を取り入れましょう。
歩く以外では足を中心にストレッチ、筋力トレーニングは骨密度にとって重要な訓練です。
まちがった姿勢で行うと体を痛めることがあります。
わからないことがあれば当院へお気軽にご相談ください。