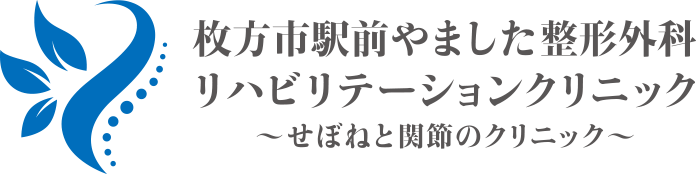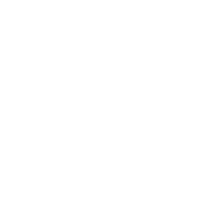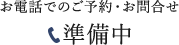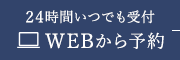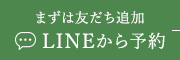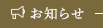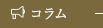- 変形性関節症とは
- 変形性関節症とリウマチの違い
- 変形性関節症が多い部位は?
- 変形性膝関節症の原因
- 変形性膝関節症になりやすい人
- 変形性膝関節症の初期症状
- 変形性膝関節症の検査・診断
- 変形性膝関節症の治療
- 変形性膝関節症でやってはいけないこと
- 変形性関節症で障害者手帳を取得できる?
変形性関節症とは
 変形性関節症は、関節の軟骨がすり減り、最終的に関節が変形する進行性の病気です。
変形性関節症は、関節の軟骨がすり減り、最終的に関節が変形する進行性の病気です。
軟骨は骨の表面を覆い、クッションの役割を果たす組織ですが、加齢や過度な負担、遺伝的要因、過去の関節損傷などによって損傷を受け、徐々に失われていきます。
軟骨がすり減ると、骨同士が直接こすれ合うようになり、痛みや炎症が生じます。
症状はゆっくりと進行し、初期には「動き始めに痛む」「関節がこわばる」といった症状が見られます。
病気が進行するにつれて、関節の痛みが安静時にも現れるようになり、関節を動かせる範囲(可動域)が狭まります。
さらに、関節が腫れたり、関節の周りの骨が変形して「O脚」や「X脚」になるなど、外見上の変化も生じることがあります。
特に、体重がかかる膝関節や股関節、頻繁に使う手の指の関節、そして脊椎などによく見られます。
日常生活における動作が困難になることもあり、生活の質に大きく影響を及ぼす可能性があります。
変形性関節症とリウマチの違い
変形性関節症と関節リウマチは、どちらも関節の痛みや腫れを引き起こす病気ですが、その原因やメカニズムは大きく異なります。
しかし、特に初診時や初期の段階では症状が似ているため、専門医でも見分けるのが難しいことがあります。
変形性関節症は、関節の軟骨がすり減ることが原因で起こる「使いすぎ」や「加齢」による病気です。痛みは、体を動かし始めるときや、長時間同じ姿勢でいた後に現れることが多いのが特徴です。
一方、関節リウマチは、自己免疫の調節異常によって全身の関節に炎症が起こる病気です。
朝起きた時の強いこわばり、複数の関節に同時に痛みや腫れが出ることがありますが、これらはリウマチだけの症状ではありません。
こうした症状の違いに加えて、診断には血液検査が重要な役割を果たします。関節リウマチでは、自己抗体が陽性になったり、炎症反応が高値になったりすることが多く、これらの検査は変形性関節症では通常陰性です。しかし、関節リウマチでも血液検査が陰性の「血清反応陰性関節リウマチ」も存在するため、血液検査だけで明確な診断を下すことはできません。
そのため、当院では初診で関節の痛みや腫れのある患者さんには、鑑別診断のためにリウマチの血液検査を行うことがあります。
加えて画像検査も併用し、総合的に判断することで、適切な診断と治療につなげていきます。
変形性関節症が多い部位は?
変形性関節症は、体の様々な関節に起こりますが、特に負担がかかりやすい場所に多く見られます。代表的なのは、膝関節です。歩いたり立ったりと、常に体重を支えるため、軟骨がすり減りやすいからです。
次に多いのは、股関節です。こちらも体重を支える重要な関節で、加齢や使い方によって変形が進みやすい傾向があります。
他にも、手指の関節(特に指の第一関節や親指の付け根)や、首や腰の脊椎も、日常的な動きで負担がかかりやすく、変形性関節症が見られる部位です。
変形性膝関節症の原因
変形性膝関節症の主な原因は、膝関節の軟骨が徐々にすり減り、関節の変形や痛みが生じる病気です。発症には、いくつかの要因が複合的に関与しています。
加齢
最も大きな原因は加齢です。年齢を重ねるにつれて、軟骨の水分量が減り、弾力性が失われるため、損傷しやすくなります。その結果、歩行や立ち座りといった日常動作でも軟骨が傷つきやすくなり、膝関節のすり減りが進行します。
膝への過度な負担
体重が増えると、膝関節には体重の数倍もの負荷がかかります。BMIが高い方では、膝への負担が大きくなり、軟骨の摩耗が進みやすくなります。また、長時間の立ち仕事、重労働、膝を酷使するスポーツも原因の一つです。O脚・X脚などのアライメント異常や、膝に負担のかかる歩き方も影響します。
過去の膝のケガ
半月板損傷や靭帯損傷、骨折など、過去の膝の外傷は関節の安定性を低下させます。その結果、膝関節に偏った力がかかり、軟骨のすり減りが早まることがあります。
遺伝
家族に変形性膝関節症の人がいる場合、発症しやすい傾向があります。
性別
性別も影響し、女性に多く見られる傾向があります。特に閉経後の女性は、ホルモンバランスの変化が軟骨に影響するとも言われています。
これらの要因が単独ではなく複合的に作用し、軟骨の変性や破壊を促進し、変形性関節症の原因となってしまいます。
変形性膝関節症になりやすい人
高齢の方
加齢により膝関節の軟骨が徐々にすり減り、クッション機能が低下するため、発症リスクが高くなります。
体重が多い方(BMIが高い方)
膝関節には歩行時に体重の数倍の負荷がかかります。体重増加により膝への負担が大きくなり、軟骨の摩耗が進みやすくなります。
女性(特に閉経後)
変形性膝関節症は男性より女性に多く、閉経後は女性ホルモンの変化により軟骨の代謝が低下することが影響すると考えられています。
膝を酷使するスポーツを行っている方
ランニング、サッカー、バスケットボール、登山など、膝に繰り返し強い負担がかかるスポーツは、軟骨のすり減りを早める原因となります。
膝に負担のかかる仕事に従事している方
長時間の立ち仕事、重い物を持つ作業、膝の曲げ伸ばしを繰り返す作業が多い職業では、膝関節への負荷が蓄積しやすくなります。
過去に膝をケガしたことがある方
半月板損傷や靭帯損傷、膝周囲の骨折などの既往があると、関節の安定性が低下し、変形性膝関節症を発症しやすくなります。
O脚・X脚など膝の配列に異常がある方
膝関節にかかる力が偏り、特定の部位の軟骨が集中的にすり減りやすくなります。
遺伝的な要因がある方
家族に変形性膝関節症の方がいる場合、体質的に発症しやすい傾向があります。
骨粗鬆症がある方
骨の強度が低下すると、膝関節の支持性が弱まり、関節への負担が増えることがあります。
糖尿病などの代謝性疾患がある方
代謝異常は軟骨や骨の状態に影響し、変形性膝関節症のリスクを高めるとされています。
変形性膝関節症の初期症状
- 歩き始めの膝の痛み
- 膝のこわばり
- 膝の違和感・だるさ
- 長時間歩行時の膝の痛み
- 階段の昇降時の膝の痛み
- 天候による膝症状の悪化
- 膝を動かす際のギーギーとした音
- 軽度の膝の腫れ
- 膝の動かしにくさ
- 特定の動作時のみに生じる膝の痛み
変形性膝関節症の検査・診断
毎回すべての検査を行うわけではなく、必要な時に必要な検査を受けていただくことが重要です。
X線(レントゲン)検査
最も基本的な検査で、骨の状態を評価します。
軟骨自体はレントゲンには写りませんが、軟骨がすり減ると関節の隙間が狭く見えたり、骨棘(こつきょく:骨のとげ)の形成、骨の硬化、骨嚢胞などの変形性関節症に特徴的な所見を確認できます。特に、体重がかかる状態で撮影することが重要です。
超音波(エコー)検査
超音波を用いてリアルタイムで関節の状態を評価できる検査です。レントゲンでは見えにくい関節を包む袋の中の関節液の貯留(水がたまること)、関節の周りの滑膜(かつまく)の炎症や肥厚、さらには半月板の逸脱や関節周囲の腱・靭帯の異常などを確認できます。痛みのある部分をリアルタイムで確認できるため、診察と合わせて痛みの原因を特定するのに役立ちます。放射線被ばくがなく検査を受けてもらえる利点もあります。
MRI(磁気共鳴画像)検査
レントゲンやエコーでは評価が難しい軟骨内部の変化、骨の内部の状態、半月板や靭帯などの軟部組織の状態を評価できます。
初期の軟骨損傷や、関節液の貯留、骨の内部の炎症なども確認できるため、早期診断や詳細な病態把握に有用です。
当院はMRIがないため、提携病院での検査を受けていただくこととなります。
血液検査
変形性関節症自体では、炎症を示す数値(CRPや赤沈)は通常正常か軽度の上昇にとどまります。しかし、関節リウマチや他の炎症性関節炎との鑑別が必要な場合に、リウマトイド因子や抗CCP抗体などの自己抗体、尿酸値などを調べるために行われます。
関節液検査
関節に水がたまっている(関節水腫)場合、関節液を採取して、その成分を調べることがあります。これにより、感染症や痛風などの他の関節疾患と変形性関節症を鑑別できます。
これらの検査結果と診察所見を総合的に判断して、変形性関節症とそれ以外の診断を行う、病状の進行度(重症度)を評価します。
変形性膝関節症はレントゲンでわかる?

変形性膝関節症は、X線(レントゲン)検査で診断可能です。軟骨自体は写りませんが、軟骨がすり減ることで関節の隙間が狭くなったり、骨棘(骨のとげ)ができたり、骨が硬くなったりといった特徴的な変化が骨に現れます。これらの骨の変化から、軟骨のすり減り具合や病気の進行度を推測できます。特に、立った状態で撮影することで、体重がかかった状態での関節の隙間を正確に評価することが重要です。ただし、初期の段階ではレントゲンでは変化が分かりにくい場合もあります。また、他の検査と組み合わせて総合的に診断を受けていただくことが適切な治療の第一歩となります。

変形性膝関節症の治療
変形性膝関節症の治療は、病気の進行度や患者さんの状態に合わせて様々な方法を用います。当院では、主に以下のような治療を行っています。
保存的治療(手術以外の治療)
薬物療法
痛みを和らげるための内服薬(消炎鎮痛剤)や、関節の炎症を抑えるための貼り薬、塗り薬などを処方します。
リハビテーション
関節の負担を減らすための筋力強化運動、関節の可動域を広げるストレッチ、姿勢の改善指導などを行います。
当院では理学療法士が個別の治療計画を提案いたします。

物理療法
温熱療法や電気療法などを用いて、血行を促進し、痛みの軽減を図ります。
装具療法
サポーターや足底板(インソール)などを用いて、関節にかかる負担を軽減し、安定性を高め、生活の質を高めることを目的としています。
関節内注射
ヒアルロン酸注射
軟骨の動きを滑らかにし、痛みを和らげる効果が期待できます。
ステロイド注射
関節の強い炎症を抑え、急性の痛みを軽減します。連用はできないことが多いです。
再生医療
近年注目されている治療法として、PRP(多血小板血漿)、PFC-FD(血小板由来因子濃縮物凍結乾燥精製)療法があります。これは、患者さんご自身の血液から血小板を多く含む成分を抽出し、それを患部の関節に注入する治療法です。
血小板には組織の修復を促す成長因子が豊富に含まれており、炎症を調節し、痛みを軽減する効果が期待できます。
ご自身の血液を使うため、アレルギー反応などのリスクが少ないというメリットもあります。
この治療は、特に従来の保存療法では効果が限定的であったものの、手術には抵抗がある方や、手術が必要なほど進行していない方に適応となる場合があります。
詳しくは当院PRP、PFC-FD療法に詳しく書いていますのでご覧ください。
手術療法
保存的治療や再生医療でも改善が見られない場合や、症状が進行して日常生活に大きな支障をきたしている場合には、手術を検討します。
当院では手術は行っておらず、患者さんの状態とご希望に応じて、提携している高度医療機関にご紹介し、専門医による適切な手術(関節鏡手術、骨切り術、人工関節置換術など)を受けていただけるよう手配いたします。
変形性膝関節症は
進行するとどうなる?
 変形性膝関節症は進行するとどうなる?痛みが慢性化し、安静時や夜間にも痛みを感じるようになり、睡眠が妨げられることもあります。関節の軟骨がさらにすり減ると、骨同士が直接こすれ合うため、激しい痛みが生じ、関節の炎症も強くなります。
変形性膝関節症は進行するとどうなる?痛みが慢性化し、安静時や夜間にも痛みを感じるようになり、睡眠が妨げられることもあります。関節の軟骨がさらにすり減ると、骨同士が直接こすれ合うため、激しい痛みが生じ、関節の炎症も強くなります。
これにより、関節の可動域が著しく制限され、膝であれば正座ができない、完全に伸びない、曲がらないといった状態になります。歩行も困難になり、杖や歩行器が必要になったり、O脚やX脚といった目に見える変形が進んだりすることもあります。
また、痛みをかばうことで周囲の筋肉が衰え(筋力低下)、さらに身体活動が減少するという悪循環に陥りやすくなります。最終的には、外出が億劫になり、引きこもりがちになるなど、生活の質(QOL)が著しく低下する可能性があります。
このように、変形性膝関節症は放置すると進行し、生活に大きな影響を及ぼす病気です。
少しでも関節の痛みや違和感を覚えたら、早めに整形外科専門医を受診し、適切な診断と治療を受けることが大切です。早期に介入することで、症状の悪化を防ぎ、快適な日常生活を長く続けることにつながります。
当院では整形外科専門医である院長が診療を行います。お気軽にご相談ください。
変形性膝関節症は治る?
すり減ってしまった膝関節の軟骨を、完全に元の状態へ戻すことは、現在の医療では難しいとされています。そのため、変形性膝関節症は「完全に治る病気」というよりも、「痛みや症状をコントロールしながら、進行を抑えて付き合っていく病気」と考えられています。
ただし、治療が無意味というわけではありません。早期に適切な治療を開始することで、膝の痛みを軽減し、動かしやすさを改善し、日常生活への支障を少なくすることが可能です。また、症状の進行を遅らせる効果も期待できます。
治療には、痛み止めなどの薬物療法、膝周囲の筋力を鍛える運動療法、装具療法、注射治療、再生医療などを、患者さんの症状や生活スタイルに合わせて組み合わせて行います。多くの患者さんが、適切な治療を継続することで、膝の痛みを抑えながら快適な日常生活を送れるようになります。
膝の痛みを我慢せず、早めに専門医へ相談し、ご自身に合った治療を継続することが大切です。膝の違和感や痛みが気になる方は、どうぞお気軽に当院へご相談ください。
変形性膝関節症は
歩いたほうが良い?
変形性膝関節症で膝が痛いと、「歩かない方がいいのかな?」と考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、適切な範囲で体を動かすことは、むしろ膝関節にとって良い影響をもたらすことが多いです。
なぜ歩いた方が良いのか?
全く動かさないでいると、膝を支える筋肉が衰えてしまい、かえって膝への負担が増してしまいます。また、関節の動きも悪くなり、ますます痛みを感じやすくなる悪循環に陥ってしまう可能性もあります。
適度に歩くことで、以下のようなメリットが期待できます。
- 膝周りの筋肉を維持・強化できる
- 関節の動きを滑らかにする
- 体重管理にもつながる
ただし、やみくもに歩けば良いというわけではありません。痛みがあるのに無理に歩きすぎると、かえって症状を悪化させてしまうこともあります。
ポイントとして、
- 痛みのない範囲
- 短い時間から少しずつ
- 平らな道を選ぶ
- 患者さんそれぞれに適した靴を履く
が挙げられます。
「じゃあ、どれくらい歩けばいいの?」と迷う方もいらっしゃるでしょう。
その方の膝の状態や痛みの程度によって、適切な運動量や種類は異なります。自己判断で無理をしてしまうと、かえって悪化させてしまうリスクもあります。
そのため、まずは整形外科を受診して、状態を適切に把握する必要があります。
その上で、整形外科医、理学療法士から、ご自身に合った適切なリハビリテーションや運動指導を受けることが非常に重要です。
正しい知識と方法で体を動かしましょう。
当院では皆様の快適な生活を過ごせるようお手伝いをさせていただきます。
変形性膝関節症で
やってはいけないこと
- 膝の痛みを我慢して無理に運動を続けること
- 急な動きや方向転換を伴う運動をする
- 膝を深く曲げる動作
- 重いものを持ち上げる・運ぶ
- 長時間の立ち仕事や歩行
- 運動不足で筋力を低下させる
- BMIが高い状態(体重増加)を放置する
- ヒールの高い靴を履く
- 床に直接座る生活スタイル
- 喫煙や過度な飲酒
- 膝を冷やしすぎること
- 自己判断で症状を放置する
変形性関節症で
障害者手帳を取得できる?
変形性膝関節症の症状が重く、膝の機能障害により歩行や立ち上がりなどの日常生活動作に著しい制限がある場合、身体障害者手帳を取得できる可能性があります。
ただし、「変形性膝関節症」と診断された時点ですぐに手帳が交付されるわけではありません。膝関節の可動域制限や歩行能力の低下の程度などについて、国が定める身体障害認定基準を満たしているかどうかが判断されます。
症状の程度や治療状況によって認定の可否は異なるため、手帳の取得を検討されている場合は、主治医や医療機関、またはお住まいの自治体の窓口へ相談することが大切です。
身体障害者手帳の認定基準
身体障害者手帳の認定基準は、障害の種類や程度によって細かく定められています。変形性関節症の場合、「肢体不自由」の項目で評価されます。
関節の機能障害の程度、日常生活への影響を診断書に書いて、最終的には市役所の方で判断をされます。
人工関節置換術の場合
2014年4月以降に基準が改正され、現在は、人工関節の手術をうけられた後に自動的に認定されるわけではなく、術後の関節の機能障害の程度(可動域、筋力など)を評価し、その状態に応じて等級が判断されます。術後の経過が良好で、機能がかなり改善している場合は、手帳の対象とならないことも多くあります。
申請について
身体障害者手帳の申請は、以下の流れで進めていただきます。
1診断書の取得
指定医(身体障害者福祉法第15条指定医)が作成する診断書が必要です。当院で書けるのは「肢体不自由」のみとなります。
当院に相談し、手帳の申請が可能か確認をしてください。診断書作成は保険適応外のため8,000円(税抜)となります。角度の計測などが必要なため、別日で理学療法士による計測日が必要となります。
ここからは患者さんが行う手続きです。
2市町村の窓口に申請
診断書や必要書類を揃えて、お住まいの市町村の福祉担当窓口に申請します。
3審査
提出された書類に基づいてお住いの市町村にて審査が行われます。審査基準などは当院ではわかりかねますのでお住いの市町村へお問い合わせください。
4手帳の交付
認定基準を満たしていると判断されれば、市町村より身体障害者手帳が交付されます。