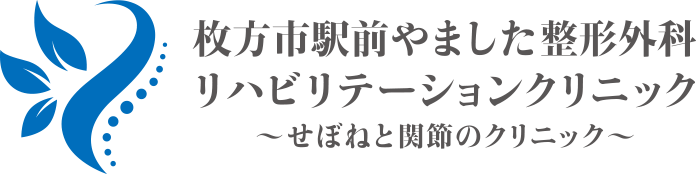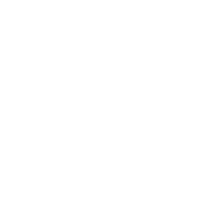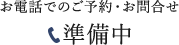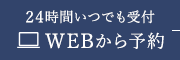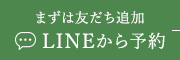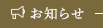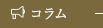- 四十肩・五十肩の正式名称は肩関節周囲炎?
- 四十肩・五十肩の原因
- 四十肩・五十肩にならない人の特徴
- 「腕が上がらない」「二の腕が痛い」のは四十肩・五十肩?
- 四十肩・五十肩の検査・診断
- 四十肩・五十肩の治療
四十肩・五十肩の正式名称は
肩関節周囲炎?
 四十肩・五十肩の正式名称は「肩関節周囲炎(かたかんせつしゅういえん)」です。
四十肩・五十肩の正式名称は「肩関節周囲炎(かたかんせつしゅういえん)」です。
これは、肩関節の周りにある腱板、関節包、滑液包といった組織に炎症が起きることで、肩の痛みや動きの制限を引き起こす病気の総称です。四十肩や五十肩という呼び方は、この症状が40代から50代にかけて多く見られることにちなんだ通称であり、医学的な正式名称ではありません。しかし、一般的には広く知られていますが、整形外科以外のお医者さんとの会話では理解してもらえないことがあるようです。当院では「四十肩・五十肩かもしれない」といった症状でも診察可能です。お気軽にご相談ください。
四十肩と五十肩の違い
四十肩と五十肩は、基本的に同じ病態である「肩関節周囲炎(かたかんせつしゅういえん)」を指す通称です。医学的な区別は明確にはありません。
四十肩、五十肩という呼び方は、症状が40代で現れた場合に「四十肩」、50代で現れた場合に「五十肩」と呼ばれるようになったものです。
したがって、症状そのものに大きな違いはなく、どちらも肩関節の周囲の組織に炎症が起こり、肩の痛みと動きの制限を主な症状とします。
四十肩・五十肩の原因
四十肩・五十肩(肩関節周囲炎)の明確な原因は、実はまだはっきりと解明されていません。
しかし、現在考えられている主な要因としては、以下のものがあります。
加齢に伴う組織の変性
肩関節を構成する筋肉、関節を包む袋、靭帯などの組織が、加齢とともに柔軟性や弾力性が減少し、変性し始めていくことが考えられています。これらの組織が原因で、日常動作や重くない負荷でも炎症を起こしやすくなってしまいます。
肩関節への負担
長年の仕事やスポーツ、日常生活での繰り返し動作などによる肩への負担が、組織の炎症や損傷を引き起こす可能性があります。特に、若い頃に肩を酷使した経験のある人は、発症リスクが高まると言われています。
生活習慣病との関連
喫煙、糖尿病、高血圧、脂質異常症などの生活習慣病は、血行不良を引き起こし、肩関節周囲の組織への酸素や回復に役立つ成分の供給を妨げる可能性があります。
これにより、組織の修復が遅れ、炎症が慢性化しやすくなることがあります。
このように、四十肩・五十肩は、単一の原因で起こるのではなく、加齢による組織の変化を基盤として、肩への負担や生活習慣病、その他の様々な要因が複雑に関与して発症すると考えられています。
四十肩・五十肩に
ならない人の特徴
四十肩・五十肩(肩関節周囲炎)になりにくい人には、いくつかの共通する特徴が見られます。
まず、肩周りの柔軟性が高く、可動域が広いことが挙げられます。
日頃からストレッチや適度な運動を習慣にしている人は、肩関節の組織が硬くなりにくく、炎症のリスクを減らせます。
次に、良い姿勢を保っていることも重要です。
また、肩に過度な負担をかけない生活習慣も大切です。重い物を頻繁に持ち上げたり、同じ動作を繰り返したりする作業は、肩関節に慢性的な微細な損傷を引き起こす可能性があります。
これらの習慣を持つ人が必ずしも四十肩・五十肩にならないわけではありませんが、発症のリスクを抑える可能性があると考えられます。
「腕が上がらない」
「二の腕が痛い」のは
四十肩・五十肩?
 「腕が上がらない」「二の腕が痛い」といった症状は、四十肩・五十肩(肩関節周囲炎)の可能性があります。
「腕が上がらない」「二の腕が痛い」といった症状は、四十肩・五十肩(肩関節周囲炎)の可能性があります。
四十肩・五十肩では、肩関節の炎症により、動かす時の痛みや夜間痛に加え、腕を上げる、ひねるなどの動作が制限されます。
痛みは肩だけでなく、二の腕や肩甲骨周囲に広がることもあります。
神経症状との簡易的な鑑別では、しびれの有無が重要です。四十肩・五十肩では通常しびれは伴いません。もし、腕や手のしびれ、力が入りにくいといった症状がある場合は、神経が圧迫される病気の可能性を考慮する必要があります。ただし、しびれを伴わない場合も神経の症状をみていることがあります。
自己判断は難しく、症状が続く場合は整形外科専門医を受診し、診察を受けることが大切です。
四十肩・五十肩は片方の肩だけなることもある?
四十肩・五十肩(肩関節周囲炎)は、片方の肩だけに起こることもあります。左右どちらの肩にも発症する可能性がありますが、初期は片側だけに症状が現れるケースが多いです。
ただし、一度片方の肩が四十肩・五十肩になると、数ヶ月から数年後に反対側の肩にも同様の症状が出ることがあります。
これは、体の使い方や姿勢の偏り、加齢による組織の変化などが両肩に影響を与えるためと考えられています。
そのため、「片方だけだから大丈夫」とは言えず、症状が出た場合は適切な治療とケアが大切です。
また、両肩同時に発症することも稀にあります。
四十肩・五十肩の検査・診断
四十肩・五十肩(肩関節周囲炎)の診察。検査と診断は難しく、専門的な知識を持つ整形外科専門医による診察を受けることが望ましいです。
診断の最初の段階では、患者さんの症状や動きの制限の程度などのお困りの症状を問診、可動域の確認、徒手検査にてそれぞれの筋肉、関節包の固さなどの診察を行います。
画像検査としては、レントゲン検査が基本となります。レントゲンでは、骨折や脱臼、関節の変形、石灰化など、他の病気が隠れていないかを確認するために行われます。
初回の診察で四十肩・五十肩の可能性が高いと判断された場合でも、その後の経過観察や治療の効果判定のために、2回目以降の診察でエコー(超音波)検査を行うことがあります。
エコー検査では、炎症の程度の確認、関節内の液体の貯留などをより詳しく評価することができます。
必要に応じて、MRI検査などのさらに詳しい画像検査を行うこともあります。
これらの検査結果と臨床所見を総合的に判断し、四十肩・五十肩であるかどうかの診断を行います
四十肩・五十肩の治療
四十肩・五十肩は、痛みの時期と動きの制限の程度で治療内容が異なります。
最初の痛みが強い時期
安静を基本とし、炎症を抑えるための湿布や内服薬(消炎鎮痛剤)を用います。
痛みがひどい場合には、関節内外へのステロイド注射が行うこともあります。
この際、当院へ必要にあわせてエコーを用いて病変部位への選択的な注射を行います。
痛みが落ち着いてきた時期
痛みが落ち着いてきたら、動きの制限の改善が中心となります。
温熱療法や物理療法(電気治療など)で肩周りの血行を促進し、硬くなった関節包や筋肉を柔らかくしていきます。
理学療法士による理学療法も非常に重要でこの時期から行っていきます。
ご自宅でできる重要なことは、ご自身で行う運動療法(リハビリテーション)です。
理学療法士による指導も行います。焦らず根気強く続けることが大切です。
痛みがあまりにも強い場合や、保存療法で改善が見られない場合には、手術が検討さます。多くの場合、お薬や注射とリハビリテーションによって症状の改善が期待できます。根気強く治療に取り組むことが重要です。
四十肩・五十肩は放置しても治る?
四十肩・五十肩(肩関節周囲炎)は、放置しても自然に治る可能性はあります。
数ヶ月から1~3年程度の時間をかけて、痛みや動きの制限が徐々に改善していく患者さんもいます。
しかし、放置することで以下のようなデメリットが考えられます。
- 回復に時間がかかる: 適切な治療やリハビリテーションを行わない場合、自然治癒までに予想以上に長い期間を要することがあります。
- 動きの制限が残る: 炎症が長引いたり、肩を動かさない期間が続いたりすると、関節が硬くなってしまうことがあります。硬くなってしまい肩を動かせなくなると、手術を要する場合もあります
- 痛みが慢性化する: 適切な痛みのコントロールを行わないと、痛みが長期化し、日常生活に支障をきたすことがあります。
肩の痛みの中には、腱板断裂や変形性関節症など、経過で改善しない可能性のある病気が隠れている場合があります。
自己判断で放置せず、整形外科医の診断を受けることが重要です。
したがって、四十肩・五十肩は自然に治る可能性はあるものの、適切な治療とリハビリテーションを行うことで、症状の早期改善や後遺症の軽減が期待できます。
「そのうち治るだろう」と安易に放置せず、症状が出たら整形外科を受診し、治療方針を決めることをお勧めします。
四十肩・五十肩は温める・冷やすどちらが良い?
四十肩・五十肩の治療において、温めるか冷やすかは、症状の時期によって異なります。
最初の痛みが強い時期には、冷やすことを推奨します。
炎症が起こっている患部を冷やすことで、炎症の拡大を抑え、痛みを軽減する効果が期待できます。凍傷に気を付けて氷嚢などで冷やすことで痛みの軽減を図ります。
慢性的な痛みや動きの制限が主な時期には、温めることが有効な場合が多いです。
温めることで血行が促進され、筋肉や関節が柔らかくなり、動きの範囲が広がりやすくなります。特に冬は体が冷えやすいので注意が必要です。
ただし、ご自身の症状がどの時期にあるのかを正確に判断するのは難しい場合があります。自己判断せずに、整形外科を受診し、適切な温め方・冷やし方のアドバイスを受けるようにしてください。