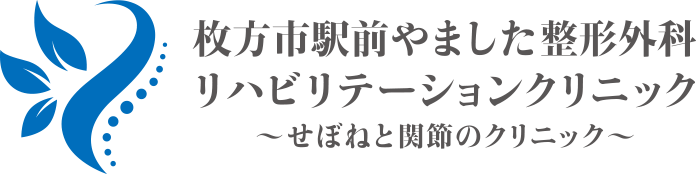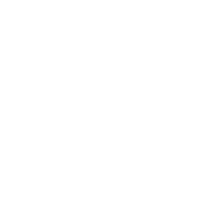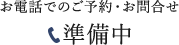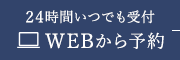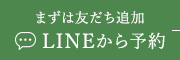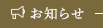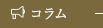肘の痛み症状はありませんか?
以下のような症状がありましたら、当院までご相談ください。
- 肘を曲げたり伸ばしたりすると痛い
- 重い物を持つとズキッと痛む
- 肘の外側(内側)が押すと痛い
- ペットボトルのフタを開けるのがつらい
- タオルをしぼる動作で肘に痛みが走る
- ゴルフやテニスをした後に痛みが強くなる
- デスクワークのあとにジンジンする
- 朝起きたときに肘がこわばる
- 肘のあたりが腫れていて熱っぽい
- 子どもを抱っこしたときに痛みが出る
- 肘を使いすぎるとあとから痛くなる
- 何もしていなくてもジンジン痛むことがある
- 肘から手首までしびれるような感覚がある
- 肘をつくと痛いので机に腕を置けない
- 重い鍋を持つのがつらい
- 肘がカクカクしてスムーズに動かせない
- 以前より肘が曲がりにくい・伸ばしにくい
- 肘の関節の奥がズーンと重だるい感じ
- 押すと痛い部分がピンポイントである
- 服を脱ぎ着するときに肘に違和感がある
- 肘の内側に電気が走るような痛みがある
- 肘を伸ばしきるとピキッとする
- 洗い物をしているときに痛くなる
- 買い物袋を持つと痛くて手を替える
- ドアノブをひねるのがつらい
- 肘をねじる動作ができない・痛い
- 肘のあたりの皮膚が敏感になっている気がする
など
肘の痛みの原因
テニス肘(外側上顆炎)
テニス肘は、肘の外側にある腱が繰り返しの使用によって炎症を起こす病気です。ラケットスポーツをしない人でも、パソコン作業や荷物の持ち運びなど、手首をよく使う作業が原因で起こることがあります。肘の外側に痛みがあり、物をつかんで持ち上げる動作で特に痛みが強くなります。進行すると、日常生活に支障をきたすこともあるため、早期の診断、対処が重要です。
ゴルフ肘(内側上顆炎)
ゴルフ肘は、肘の内側に痛みが出る病気で、テニス肘とは反対側の内側に発生します。ゴルフのスイング動作に似た、手首を内側に曲げる動作の繰り返しで発症します。重い物を持ち上げたり、ドアノブを回したりする動きで痛みを感じるのが特徴です。家事やスポーツ、仕事で腕を酷使する人に多く、安静やストレッチ、物理療法、リハビリテーションが治療に効果的です。
変形性肘関節症
加齢や過去のけが、使い過ぎにより肘の関節の軟骨がすり減ってしまう状態です。肘を動かすと「ゴリゴリ」と音がする、伸びきらない・曲げきれない、などの症状が出てきます。炎症を伴うと、肘に腫れや熱感を感じることもあります。関節の動きが制限されてくると、生活に支障が出るため、リハビリテーションや痛み止め、場合によっては手術が検討されることもあります。
肘部管症候群
肘の内側を通る尺骨神経(小指側を支配する神経)が圧迫されて起こる病気です。長時間の肘の曲げ伸ばしや、骨の変形、ガングリオン(良性の腫瘍)が原因となることがありますが原因はわからないこともあります。初期には小指や薬指のしびれが現れ、進行すると手指の細かい動きがしづらくなったり、筋力が低下したりします。症状が強い場合は、神経の圧迫を和らげる手術が行われることがあります。
離断性骨軟骨炎(OCD)
特に成長期の子どもや10代のスポーツ選手に見られる肘の障害です。肘の骨の一部が壊死し、軟骨が剥がれて関節内で痛みや引っかかりが生じます。野球の投球動作や体操など、肘を繰り返し使う動作が原因です。初期には軽い痛みだけですが、進行するとロッキング(関節が引っかかって動かなくなる)や運動制限が見られます。初期なら安静で改善することもありますが、進行していれば手術が検討されます。
肘靱帯損傷・肘関節の捻挫
転倒やスポーツ時の衝撃などにより、肘の靱帯が伸びたり切れたりすることで痛みが起こります。肘を動かすと痛みが出るほか、腫れや内出血がみられることもあります。特に野球や柔道など、腕に強い力が加わる競技で起こりやすいです。軽度なら安静と冷却で回復しますが、靱帯の損傷が大きい場合には装具や手術が必要になることもあります。
関節リウマチ
自己免疫の異常により関節に慢性的な炎症が起こる病気です。手や指の関節から始まることが多いですが、肘関節にも症状が出ることがあります。初期は腫れや軽い痛みだけでも、進行すると関節の変形や動かしづらさが生じます。両側の肘に症状が出ることが多く、早期の診断と治療(抗リウマチ薬など)が重要です。
神経障害
(頚椎疾患からの放散痛)
肘自体に問題がなくても、首の神経(頚椎)から出た神経が圧迫されることで、肘の痛みやしびれが出ることがあります。例えば、頚椎症や椎間板ヘルニアが原因です。この場合、肘だけでなく腕や肩、指先にも症状が及ぶことがあります。肘の局所治療だけでなく、頚椎の状態も確認する必要があります。
スマホで肘が痛くなる?
 スマートフォン(スマホ)の仕様で肘が痛くなることがあります。この状態を通称「スマホ肘」といい、スマートフォンを長時間持ち続けたり、肘を曲げたまま操作を続けることで、肘の内側にある尺骨神経に負担がかかり、「肘部管症候群」を引き起こすこともあります。主な症状としては、小指や薬指のしびれや肘の内側の違和感・痛み、手に力が入りづらくなる、肘を曲げると悪化するといったものがあります。肘を曲げた状態でスマホを長時間使用する、頬杖をついたままスマホを見ることがリスク要因となりますので、注意が必要です。
スマートフォン(スマホ)の仕様で肘が痛くなることがあります。この状態を通称「スマホ肘」といい、スマートフォンを長時間持ち続けたり、肘を曲げたまま操作を続けることで、肘の内側にある尺骨神経に負担がかかり、「肘部管症候群」を引き起こすこともあります。主な症状としては、小指や薬指のしびれや肘の内側の違和感・痛み、手に力が入りづらくなる、肘を曲げると悪化するといったものがあります。肘を曲げた状態でスマホを長時間使用する、頬杖をついたままスマホを見ることがリスク要因となりますので、注意が必要です。
肘の痛みはがんのサイン?
 肘の痛みの多くは関節や筋肉、神経などの整形外科的な原因によるもので、がんが原因となることは非常にまれです。ただし、安静にしていても痛む、夜間に強くなる、原因が思い当たらないのに長期間続く、腫れやしこりがある、体重減少や倦怠感などの全身症状を伴うといった場合は注意が必要です。まれに肘の骨や周囲の組織に骨腫瘍などのがんが発生することがあり、痛みとして現れることがあります。こうした異常を感じた場合は、早めにご相談ください。
肘の痛みの多くは関節や筋肉、神経などの整形外科的な原因によるもので、がんが原因となることは非常にまれです。ただし、安静にしていても痛む、夜間に強くなる、原因が思い当たらないのに長期間続く、腫れやしこりがある、体重減少や倦怠感などの全身症状を伴うといった場合は注意が必要です。まれに肘の骨や周囲の組織に骨腫瘍などのがんが発生することがあり、痛みとして現れることがあります。こうした異常を感じた場合は、早めにご相談ください。
肘の痛みがあるときの
検査・診断
問診・視診・触診
まずは痛みの場所や性質、発症の経緯(いつから、どのような動作で痛むか)などを詳しく確認します。腫れ、変形、皮下出血の有無、筋肉や腱の緊張、圧痛(押して痛む部位)などもチェックします。
関節の動きの確認
肘の曲げ伸ばしや回内・回外(手のひらの向きを変える動作)など、関節の可動域や痛みの出方を評価します。
X線検査(レントゲン)
骨折や関節変形、関節のすき間の異常などを確認します。外傷や加齢性の変化が疑われるときに有用です。
超音波検査(エコー)
腱や靭帯、滑液包の炎症などをリアルタイムで確認できます。動かしながら検査できるのが特徴です。
MRI検査
腱の断裂や関節内の異常、神経の圧迫など、より詳しい評価が必要な場合に行います。必要な場合には、連携する医療機関をご紹介いたします。
肘の痛みがあるときの
治療・対処法
安静・使いすぎの回避
肘の痛みの原因が、日常生活、スポーツや仕事などによる「使いすぎ(オーバーユース)」であることは非常に多く見られます。特に繰り返し同じ動作をすることで、筋肉や腱に微細な損傷が蓄積し、炎症や痛みを引き起こします。このような場合、まず重要なのは、痛みを感じる動作をできるだけ避けることです。無理に動かし続けると、症状が慢性化し、治りにくくなる恐れがあります。痛みが強いときには日常生活の中でも動作を制限し、関節に負担をかけない姿勢や使い方を意識することが大切です。
冷却または温熱療法
 痛みが出始めたばかりで、熱感や腫れがある場合は、アイスパックなどで患部を冷やす「アイシング」が効果的です。冷却は炎症反応を抑え、痛みや腫れを軽減します。一方、痛みが慢性化している場合や、関節が硬くこわばっている場合には、温めることで血行を促進し、筋肉の緊張をほぐす「温熱療法」が有効です。入浴や温湿布、温熱パックなどが使われます。急性期か慢性期かによって使い分けることが重要です。
痛みが出始めたばかりで、熱感や腫れがある場合は、アイスパックなどで患部を冷やす「アイシング」が効果的です。冷却は炎症反応を抑え、痛みや腫れを軽減します。一方、痛みが慢性化している場合や、関節が硬くこわばっている場合には、温めることで血行を促進し、筋肉の緊張をほぐす「温熱療法」が有効です。入浴や温湿布、温熱パックなどが使われます。急性期か慢性期かによって使い分けることが重要です。
薬物療法
痛みや炎症が強い場合には、内服薬や外用薬による薬物治療を行います。ロキソプロフェンなどの非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)を使用し、塗り薬や貼り薬の形で処方することもあります。また、症状が強く日常生活に支障が出ている場合には、局所にステロイド注射を行い、炎症を一時的に抑えることもあります。ただし、注射は繰り返し行うと腱を弱くするリスクがあるため、慎重に検討します。
装具・サポーターの使用
 テニス肘(外側上顆炎)やゴルフ肘(内側上顆炎)など、筋や腱に負担がかかることで起きる肘の痛みに対しては、専用のバンドやサポーターを使うことで、肘にかかる力を分散し、痛みを軽減することができます。特に前腕の筋肉にかかる緊張を減らすようにデザインされた装具を使用することで、日常生活や軽い作業を続けながら治療を進められる利点があります。
テニス肘(外側上顆炎)やゴルフ肘(内側上顆炎)など、筋や腱に負担がかかることで起きる肘の痛みに対しては、専用のバンドやサポーターを使うことで、肘にかかる力を分散し、痛みを軽減することができます。特に前腕の筋肉にかかる緊張を減らすようにデザインされた装具を使用することで、日常生活や軽い作業を続けながら治療を進められる利点があります。
リハビリテーション・ストレッチ
 痛みが落ち着いてきたら、関節の動きを回復させ、再発を防ぐためのリハビリテーションが重要になります。リハビリテーションでは、肘関節周囲の筋肉のストレッチや、筋力を回復させるためのトレーニングを段階的に行います。理学療法士による指導のもと、無理のない範囲で進めていきます。当院では難治性の場合、体外衝撃波を用いて治療を行うことができます。柔軟性や姿勢を整えることも、再発予防に効果的です。特にスポーツや手作業を継続する方にとっては、継続的なセルフケアの習慣化が治療の鍵になります。
痛みが落ち着いてきたら、関節の動きを回復させ、再発を防ぐためのリハビリテーションが重要になります。リハビリテーションでは、肘関節周囲の筋肉のストレッチや、筋力を回復させるためのトレーニングを段階的に行います。理学療法士による指導のもと、無理のない範囲で進めていきます。当院では難治性の場合、体外衝撃波を用いて治療を行うことができます。柔軟性や姿勢を整えることも、再発予防に効果的です。特にスポーツや手作業を継続する方にとっては、継続的なセルフケアの習慣化が治療の鍵になります。
外科的治療(手術)
保存的な治療(安静・薬・リハビリテーションなど)を数カ月続けても改善しない場合や、腱の断裂、肘部管症候群をはじめとする神経の圧迫など、明らかな構造的異常がある場合には、外科手術が検討されることもあります。たとえば、痛んだ腱の除去や修復、神経の移動・圧迫解除などが行われます。手術の種類や回復期間は症状により異なり、術後はリハビリテーションを通じて機能回復を図ることになります。当院に手術室がないため、手術は提携医療機関を手配して、依頼することになります。