頚椎症とは
頚椎症の原因
頚椎症の主な原因は加齢ですが、それ以外にもいくつかの要因が症状を悪化させたり、若年層でも発症することがあります。
長時間の不良姿勢
 デスクワークやスマートフォンの長時間使用で、うつむいたり前かがみになったりする姿勢は、頭の重さが首に大きくのしかかり、頚椎に負担をかけます。特に、猫背などの悪い姿勢が続くと、頚椎の自然なカーブが崩れ、変形が進みやすくなります。
デスクワークやスマートフォンの長時間使用で、うつむいたり前かがみになったりする姿勢は、頭の重さが首に大きくのしかかり、頚椎に負担をかけます。特に、猫背などの悪い姿勢が続くと、頚椎の自然なカーブが崩れ、変形が進みやすくなります。
首への繰り返し負担
重い物を頻繁に持ち上げる作業や、首に負担のかかるスポーツ(ラグビー、柔道、一部の水泳など)を長年行っていると、頚椎や椎間板にダメージが蓄積し、頚椎症のリスクが高まります。
また、直接の因果関係の照明は難しい場合が多いですが、昔の転倒や交通事故による外傷(むちうちなど)も、一時的に頚椎に強い衝撃を与え、頚椎症の発症につながる可能性があります。
喫煙も、血流を悪くして、変性を早める可能性があるとされています。
これらの要因が単一または複合的に作用することで、頚椎症は発症しやすくなります。
頚椎症の原因はストレス?
 ストレスが直接、首の骨の変形を引き起こして頚椎症の原因になるわけではありません。
ストレスが直接、首の骨の変形を引き起こして頚椎症の原因になるわけではありません。
しかし、ストレスが間接的に頚椎症の症状を悪化させたり、首の痛みを強く感じさせたりすることはあります。
ストレスを感じると、私たちの体は無意識のうちに首や肩の筋肉を緊張させがちです。
この筋肉の緊張が長く続くと、首周りの血行が悪くなり、筋肉が硬くなります。
その結果、首や肩のこり、痛みが強まり、頚椎に負担がかかりやすくなります。
特に、もともと加齢による頚椎の変化がある場合、ストレスによる筋肉の緊張が加わることで、症状が顕著になり、日常生活でのつらさが増すことがあります。
ストレス自体が骨や神経の病気を作るわけではなく、体の状態に影響を与えて、症状を悪化させる一因となる可能性があると理解いただくと良いかと思います
頚椎症になりやすい人
頚椎症になりやすいのは、主に首に負担がかかりやすい生活習慣や体の状態にある方です。
加齢
年齢を重ねると、首の骨と骨の間にあるクッションである椎間板が徐々に劣化し、骨が変形しやすくなるため、誰にでも起こり得る変化です。特に50代以降で多く見られます。
長時間の不良姿勢
若年層でもなりやすいのは、長時間の不良姿勢を続ける方です。
特に、パソコン作業やスマートフォンの使いすぎで、うつむいた姿勢や首が前に出た姿勢を長く続ける方は、頚椎に常に大きな負担がかかり、変形が進みやすくなります。
首に繰り返し負担がかかる
仕事やスポーツをしている
重いものを持ち運ぶ作業や、首に衝撃が加わるコンタクトスポーツなどは、頚椎へのダメージが蓄積し、発症リスクを高めることがあります。
過去に首を大きく傷つけた経験がある方も、その後の頚椎の変性が早く進むことがあります。
喫煙も血行を悪くし、椎間板の劣化を早める可能性があるため、リスクを高める要因の一つです。
頚椎症の初期症状
- 首のこり
- 首の痛み(特に動かした時)
- 肩のこり
- 肩甲骨周辺の痛み
- 腕の痛み
- 腕のだるさ
- 指先のしびれ
- 腕の感覚が鈍い
- 箸が使いにくい
- ボタンがかけにくい
- 字が書きにくい
- 腕の力が入りにくい
- 朝起きた時の首の痛みやこわばり
頚椎症の検査・診断
首の骨や神経の状態を詳しく見ます。
レントゲン検査(X線検査)
骨折の有無の確認、首の骨の並びや変形、骨のとげ(骨棘)がないかを確認します。
また、骨と骨の間の隙間が狭くなっているかどうかを検査します。
MRI検査
磁気を使って体の断面を撮影する検査で、レントゲンでは見えない椎間板(骨と骨の間のクッション)、脊髄、神経根といった柔らかい組織の状態を詳しく確認できます。神経がどの程度圧迫されているかを評価するのに非常に重要な検査の一つです。
CT検査
X線を使って体の断面を撮影する検査で、骨の細かい状態や骨棘で神経の通り道が狭くなっているかを詳しく見ることができます。
これらの診察と画像検査の結果を総合的に判断して、頚椎症であるかどうか、そしてどのような状態かを診断します。
頚椎症の治療
頚椎症の治療は、症状の程度や患者さんの状態によって様々です。
薬物療法
まず、痛みを和らげたり、炎症を抑えたりするために、薬が使われます。
痛み止め(内服薬や湿布)、筋肉の緊張を和らげる薬などが一般的です。
リハビリテーション
首の牽引療法で神経への圧迫を減らしたり、温熱療法や電気治療で痛みを和らげたりします。
また、理学療法士の指導のもと、首や肩周りの筋肉を強くしたり柔軟性を高めたりする運動やストレッチを行うことで、姿勢を改善し、首への負担を軽減します。日常生活の動作や姿勢の工夫の指導も行います。
これらの保存的な治療で症状が改善しない場合や、手足の麻痺が進んで日常生活に大きな支障が出る、排尿障害などの重い症状がある場合には、手術が検討されることもあります。
頚椎症は湿布を貼ったほうが良い?
 頚椎症で首や肩に痛みやこりがある場合、湿布を貼ることは症状の緩和に役立つことがあります。
頚椎症で首や肩に痛みやこりがある場合、湿布を貼ることは症状の緩和に役立つことがあります。
湿布には、痛みを和らげたり(鎮痛)、炎症を抑えたり(消炎)する成分が含まれているためです。
ただし、湿布はあくまで対症療法であり、頚椎症の根本的な原因を治すものではありません。
一時的に痛みを抑え生活をしやすくする目的で使用すると良いでしょう。
湿布には温感タイプと冷感タイプがありますが、どちらを選ぶかは、ご自身が心地よいと感じる方で構いません。
使用する際は、肌に異常がないか確認してから使用しましょう。
また、お風呂上がりや汗をかいている時は、皮膚への刺激が強くなることがあるので注意が必要です。
痛みが続く場合は、湿布だけで済ませずに、整形外科を受診して適切な診断と治療を受けるようにしましょう。
頚椎症を
放っておくとどうなる?
 初期の首や肩のこり、腕のしびれなどの症状は、日常生活に支障をきたすことがありますが、我慢して放っておくと症状が少しずつ変化していくことがあります。
初期の首や肩のこり、腕のしびれなどの症状は、日常生活に支障をきたすことがありますが、我慢して放っておくと症状が少しずつ変化していくことがあります。
例えば、腕や手のしびれが強くなったり、感覚が鈍くなったりすることがあります。
また、今までできていた細かい作業(箸を使う、ボタンをかけるなど)がしにくくなったり、腕や手に力が入りにくくなったりすることもあります。さらに、ごく稀にですが、足にも症状が出て、歩行が不安定になったり、尿や便に問題が出たりするケースも考えられます。
これらの症状が悪化すると、日常生活の質が低下し、不便を感じることが増えてしまうかもしれません。
症状の進行を抑え、快適な生活を長く送るためには、早めに整形外科を受診し、適切な診断と治療を受けることが大切です。
気になる症状がある場合は、一度当院にお気軽にご相談ください。
頚椎症でやってはいけないこと
 長時間同じ姿勢を続けることは避けましょう。
長時間同じ姿勢を続けることは避けましょう。
特に、スマートフォンを長時間見たり、パソコン作業を長時間行う際に、うつむきがちな姿勢は首に大きな負担をかけます。
こまめに休憩を挟み、首の位置を変えるように意識してみてください。
首に大きな負担をかける動作も控えるのが良いでしょう。
首を大きく反らして上を見る動作も避けた方が良いです。
不適切な寝姿勢も首に負担をかけることがありますので注意が必要です。
痛みやしびれがある時に、自己判断で首を強くマッサージしたり、無理なストレッチをしたりすることはかえって症状を悪化させてしまうこともあります。整形外科専門医の診断の元、理学療法士による指導を受けられることが大事です。
まずは自己判断せず、当院へお気軽に受診しご相談ください。
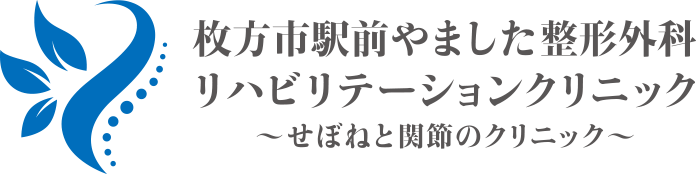

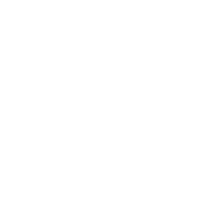
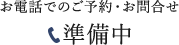
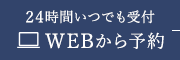
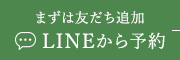
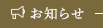
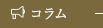


 頚椎症は、首の骨(頚椎)の加齢による首の関節や靭帯に変化が起こる病気です。
頚椎症は、首の骨(頚椎)の加齢による首の関節や靭帯に変化が起こる病気です。