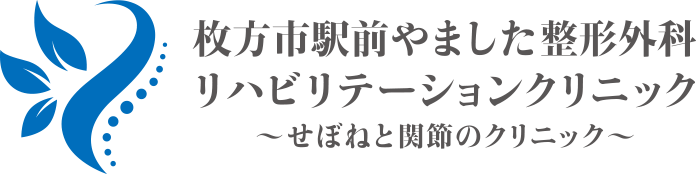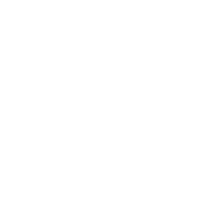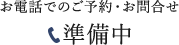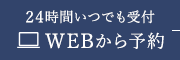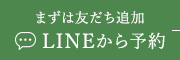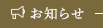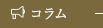ぎっくり腰の正式名称は
急性腰椎症?
 ぎっくり腰の正式名称の一つとして「急性腰痛症(きゅうせいようついしょう)」が挙げられます。
ぎっくり腰の正式名称の一つとして「急性腰痛症(きゅうせいようついしょう)」が挙げられます。
病院や医師によっては「急性腰痛症(きゅうせいようつうしょう)」や「腰椎捻挫(ようついねんざ)」といった診断名が用いられることもあります。
「急性腰痛症」という名称は、急激に発症した腰部の痛みを指し示すもので、ぎっくり腰の状態を的確に表現しています。ただし、ぎっくり腰の背景には様々な原因が考えられるため、画像診断などを行っても原因が特定できない場合も少なくありません。
ぎっくり腰の主な症状は、突然の激しい腰の痛みで、体を動かすことが困難になるほどです。
多くの場合、数日から2週間程度で自然に症状は軽減していきますが、痛みが強い場合は整形外科を受診し、治療を受けることが大切です。また、再発を予防するためには、日頃から姿勢に気をつけたり、適度な運動やストレッチで腰回りの筋肉を鍛えたりすることが重要です。当院では治療および再発予防のリハビリテーションに力を入れています。お気軽にご相談ください。
ぎっくり腰の原因
原因は一つではなく、様々な要因が複合的に関わって起こることが多いと考えられています。主な原因としては以下のものが挙げられます。
急な動作や無理な体勢
- 重い物を持ち上げる際に、腰に過度な負担がかかる
- 急に体をひねる、振り返るなどの動作
- 無理な体勢でのくしゃみや咳
- 高い所から飛び降りる、勢いよく起き上がるなどの動作
筋肉疲労の蓄積
- 長時間の立ち仕事やデスクワークなど、同じ姿勢を続けることによる腰周りの筋肉の疲労
- 運動不足による筋力低下や柔軟性の低下
- 睡眠不足や栄養バランスの偏りによる筋肉の回復遅延
骨格の歪み
- 長時間の不良姿勢(猫背、反り腰など)による骨盤や背骨の歪み
- 筋肉のアンバランスによる骨格への負担増加
その他の要因
- 加齢による背骨の変性
- 疲労やストレスによる腰の筋肉の緊張
- タバコ・冷えによる血行不良
些細な動作(物を拾う、靴下を履くなど)でも、上記のような要因が重なっている場合に急激な腰痛が起こることがあります。
ぎっくり腰は、痛みが強い場合は整形外科を受診し、治療を受けることが大切です。
ぎっくり腰になりやすい人
ぎっくり腰になりやすい人には、いくつかの共通する特徴があります。
運動不足
運動不足は、腰周りの筋肉や体幹の筋力低下を招き、腰の骨を支える力が弱まります。
これにより、ちょっとした動作でも腰の骨、筋肉に過度な負担がかかりやすくなります。また、柔軟性の低下もリスクを高めます。体が硬いと、急な動きに対応できず、ぎっくり腰を引き起こしやすくなります。
長時間同じ姿勢でいる方
デスクワークなどで長時間座りっぱなしの方や、立ち仕事で同じ体勢が続く方は、腰回りの筋肉が緊張しやすくなり、血行が悪くなります。これにより、筋肉疲労が蓄積し、ぎっくり腰のリスクが高まります。
姿勢が悪い方も同様に、特定の筋肉に負担がかかりやすく、骨格の歪みにもつながるため、ぎっくり腰になりやすいと言えます。猫背や反り腰の癖がある方は注意が必要です。
肥満気味の方
体重増加によって常に腰に負担がかかっているため、ぎっくり腰のリスクが高まります。
また、重い物を持ち上げる機会が多い仕事の方や、中腰での作業が多い方も、腰に大きな負担がかかるため、ぎっくり腰になりやすい傾向があります。
その他
加齢による椎間板や背骨の関節の変性、疲労やストレスの蓄積による腰回りの筋肉の緊張、喫煙習慣・多量飲酒・冷え性で血行が悪い方も、ぎっくり腰のリスクが高まると考えられています。
ぎっくり腰の初期症状
- 突然の腰の痛み
- 動き始もの腰の痛み
- 体勢を変える際の痛み
- 痛くて腰を伸ばせない、曲げられない
- 腰の筋肉の張りやこわばり
- 急に腰が回せない、後ろを向けない
- じっとしていても腰が痛い
- 腰の違和感や痛くなりそう予兆
ぎっくり腰は
何日目がピーク?
一般的に、ぎっくり腰の痛みのピークは発症後2~3日目と言われています。
ぎっくり腰は、急な動作や無理な体勢によって腰の筋肉や靭帯、関節などに炎症が起こることで激しい痛みが生じます。
発症直後は、比較的痛みが抑えられていることもありますが、2~3日かけて炎症が強まるため、痛みが最も強く感じられることが多いです。この時期は、体を動かすことはもちろん、安静にしているだけでも激痛に襲われることがあります。
ただし、痛みのピークやその後の回復期間には個人差があります。
痛みの程度や原因、年齢、体力などによって、ピークを迎えるまでの日数や痛みの持続期間は異なります。
多くの場合、安静と初期対処を行うことで、1週間程度で日常生活を送れる程度まで痛みは軽減していきます。しかし、完全に痛みがなくなるまでには、2週間から1ヶ月程度かかることもあります。
もし、発症後数日経っても痛みが全く改善しない、または悪化する、脚にしびれや麻痺が出てきたなどの症状がある場合は、椎間板ヘルニアなどの他の疾患が隠れている可能性も考えられます。自己判断せずに早めに整形外科を受診することが重要です。
当院では整形外科専門医が診察・診察・お薬による治療を行い、リハビリテーションは有国家資格である理学療法士が治療にあたります。
ぎっくり腰の検査・診断
当院では診察とレントゲン検査、エコー検査で行う場合が多いです。
当院では身体所見においては、患者さんの姿勢、歩き方などから始まり、整形外科専門医による診察が行われます。
これらの所見を通じて、痛みの原因となっている部位や、神経の圧迫がないかなどを評価します。ぎっくり腰の場合、多くは特定の動きで強い痛みが生じ、腰の可動域が制限されますが、足のビリビリとした神経痛は見られないことが多いです。
以下の場合は通常の検査に加えてMRI検査などの精査を行う場合があります。
- 症状が4週間以上続く慢性腰痛の場合
- 脚に強い痛みやしびれがある場合
- 排尿・排便障害がある場合
- 外傷(転倒、事故など)が原因と考えられる場合
- 腫瘍や感染症などが疑われる場合
必要と判断した場合は採血、尿検査を行う場合もあります。
身体検査や上記の検査結果との結果を総合的に判断し、ぎっくり腰であるか、他の疾患であるかの診断を行います。
専門的な診察、お薬、装具治療、リハビテーションで改善することがほとんどです。
当院へお気軽にご相談ください。
ぎっくり腰の治療
ぎっくり腰の治療は、痛みの軽減と早期の機能回復、そして再発予防を目的として行われます。
安静にする
急性期(発症から数日)には、まず安静が重要です。
無理に動かさず、楽な体勢で横になるなどして腰を休ませます。ただし、過度な安静は筋力低下を招く可能性もあるため、痛みが和らいできたら、できる範囲で少しずつ体を動かすようにします。
痛みが強い場合は、装具を使用することで、腰の安定性を高め、痛みの軽減することを狙います。
薬物療法
薬物療法としては、痛みを抑えるための鎮痛薬の内服や外用薬(湿布、塗り薬)が用います。
炎症が強い場合には、整形外科医の判断により筋弛緩薬や神経障害性疼痛治療薬などが処方することもあります。
物理療法
物理療法(機械を使ったリハビリテーション)も有効な手段の一つです。
発症直後の炎症が強い時期には、冷却療法で炎症を抑えることが有効な場合もあります。その他、低周波治療や腰椎牽引療法、理学療法士によるリハビリテーションで治療にあたります。
リハビリテーション
痛みが落ち着いてきたら、リハビリテーションを開始します。
慢性化を防ぎ、再発を予防するためには、正しい姿勢を意識すること、重い物を持ち上げる際の注意の指導を受けることなどが大切です。また、適度な運動を継続することで、腰周りの筋肉を柔軟に保ち、体幹を強化することが重要です。
ぎっくり腰の治療は、患者さんの症状や状態に合わせて個別に行います。
お気軽に当院にご相談ください。
ぎっくり腰
治りかけの症状は?
 ぎっくり腰の治りかけの時期には、急性期のつらい痛みから徐々に解放され、回復に向かっていることを示すいくつかの症状が現れます。ただし、完全に治癒するまでには個人差があり、症状の改善度合いも人それぞれです。
ぎっくり腰の治りかけの時期には、急性期のつらい痛みから徐々に解放され、回復に向かっていることを示すいくつかの症状が現れます。ただし、完全に治癒するまでには個人差があり、症状の改善度合いも人それぞれです。
まず、最も顕著な変化として挙げられるのは痛みの軽減です。
発症直後のように、体を少し動かすだけでも激痛が走るという状態から脱し、日常生活での動作、例えば歩く、座る、立つといった基本的な動作での痛みが徐々に和らいできます。
次に、腰の動ける範囲が少しずつ広がってくることが感じられます。
急性期には、前かがみや後ろ反らし、左右へかがむ、腰を回すといった腰の動きが大きく制限されていましたが、治りかけの段階では、これらの動作が以前よりもスムーズに行えるようになってきます。しかし、まだ完全に元の状態に戻っているわけではなく、無理に動かそうとすると痛みを感じることがあります。
続いて、腰周りの筋肉の張りやこわばりも徐々に和らいできます。
発症直後は、腰全体がガチガチに固まったような感覚がありましたが、徐々に筋肉が柔らかくなり、突っ張ったような感じが軽減していきます。ただし、長時間同じ姿勢を続けたり、少し無理な動きをしたりすると、再び張りを感じることがあります。
精神的な面では、激しい痛みが続いた急性期に比べ、不安感やストレスが軽減し、日常生活への復帰に向けて前向きな気持ちになることが多くなります。睡眠も比較的取りやすくなる傾向があります。
ただし、この治りかけの時期は、まだ腰が不安定な状態であり、再発の可能性があります。
油断して無理な動作をしたり、急に激しい運動をしたりすると、再び痛みが悪化してしまうことがあります。
そのため、医師や理学療法士の指示に従い、徐々に活動レベルを上げていくことが重要です。
ぎっくり腰は
どのくらいで治る?
一般的に、ぎっくり腰の治癒期間は、痛みの程度や個人の状態によって大きく異なりますが、多くの場合、以下のようになります。
| 発症から数日 | 激しい痛みが中心で、動くことが困難な場合もあります。 |
|---|---|
| 発症から1~3週間 | 痛みは徐々に軽減し、日常生活での基本的な動作が可能になってきます。 |
| 発症から2~4週間 | 日常生活のほとんどの動作が可能になりますが、まだ無理は禁物です。 |
| 発症から1~2ヶ月 | 軽めの運動やリハビリテーションを開始し、元の状態に戻ることを目指します。 |
多くの場合、強い痛みは1-2週間以内、日常生活に支障がない程度までの回復には2~4週間程度かかるとされています。
適切な治療を受けなかった場合は、2ヶ月以上かかることもあります。
自己判断で無理をすると、症状が悪化したり慢性化したりする恐れがあります。
また、ぎっくり腰は再発しやすいと言われています。痛みが引いた後も、リハビリテーションで理学療法士による指導をうけることが大事です。
お気軽に当院へ受診してご相談ください。
ぎっくり腰は
自然に回復する?
ぎっくり腰は多くの場合、自然に回復すると考えられています。
ぎっくり腰は、急な動作や無理な体勢によって腰まわりの筋肉や靭帯、関節などが一時的に損傷し、炎症を起こした状態です。
適切な安静を保ち、無理な動きを避けることで、炎症は徐々に治まっていくことがほとんどです。
一般的には、発症後1週間程度で強い痛みは軽減し、2~4週間程度で日常生活に支障がない程度まで回復することが多いです。
ただし、痛みの程度や個人の状態によって回復期間には差があり、完全に元の状態に戻るまでにはもう少し時間がかかる場合もあります。
しかし、自己判断で放置したり、無理な動きを続けたりすると、回復が遅れたり、慢性的な腰痛に移行したりする可能性もあります。また、ぎっくり腰のような激しい腰痛の裏には、椎間板ヘルニアや骨折など、他の原因が隠れている場合もあります。
お気軽に当院へ受診、ご相談ください。
ぎっくり腰で
やってはいけないこと
ぎっくり腰の際に、症状を悪化させたり回復を遅らせたりする可能性のある、やってはいけないことがあります。
無理な体勢や急な動作
痛む部分に負担をかけるような姿勢をとったり、急に体をひねったり、立ち上がったりする動作は避けましょう。
重い物を持ち上げる
腰に大きな負担がかかるため、回復まで控えるべきです。どうしても必要な場合は、膝を曲げて腰を落とし、体に近い位置で持ち上げるようにしましょう。
長時間の同一姿勢
立ったままや座ったままなど、同じ姿勢を長時間続けることは、腰まわりの筋肉を緊張させ、痛みを悪化させる可能性があります。
痛みを我慢しての
運動やストレッチ
痛みが強い時期に無理に運動やストレッチを行うと、炎症を悪化させる可能性があります。医師・理学療法士の指示に従い、適切な時期に行うようにしましょう。
急性期に腰を温めすぎる
発症直後の炎症が強い時期に温めると、炎症を助長し、痛みが悪化することがあります。
マッサージや強く揉むこと
炎症を起こしている患部を強く揉むと、さらに組織を傷つけ、痛みを悪化させる可能性があります。
中腰での作業
中腰での作業は腰に大きな負担がかかります。できるだけ避け、負担がかからないようにしましょう。
高いヒールの靴を履く
体の重心が不安定、前かがみになり、腰に負担がかかりやすくなります。
過度な安静
痛みが強い時期は安静が重要ですが、完全に動かないでいると、筋力低下を招き、回復を遅らせる可能性があります。痛みが和らいできたら、医師や理学療法士の指示に従い、徐々に体を動かすようにしましょう。
これらの点に注意し、安静にしつつ、定期的な診察、理学療法士によるケアに従って適切な治療とケアを行うことが、ぎっくり腰の早期回復につながります。