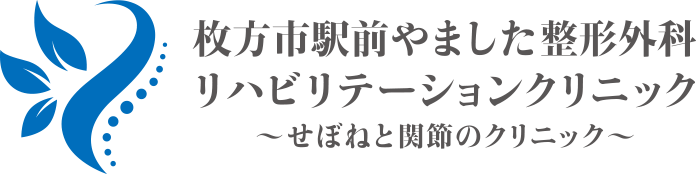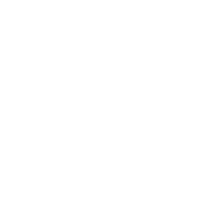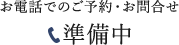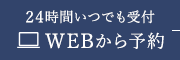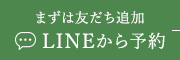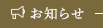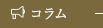交通事故に遭ったら…
 交通事故に逢ってしまわれたら落ち着いて以下の手順で対応してください。
交通事故に逢ってしまわれたら落ち着いて以下の手順で対応してください。
警察への連絡を行い、「交通事故証明書」を発行してもらう必要があります。また、相手の確認を行う必要があり、氏名、住所、連絡先(電話番号)、車両登録番号、加入している保険会社名・保険の種類・証券番号を個人情報に十分配慮して控えてください。
ご自身の保険会社への連絡も忘れず行い、担当の方に指示にしたがってください。
当然ですが何らかの症状があれば病院への受診が必要となります。
以下に記載する書類、保険のこともあり交通事故後は早めに医療機関へ受診されることをお勧めします。
交通事故後で傷んだ体で自動車を運転することは危険ですので、公共交通機関で通院することが一般的です。
当院は駅すぐで自賠責保険にて診療可能ですので、些細な症状でもお気軽に受診ください。
整形外科と
整骨院・接骨院の違い
整形外科では診断、治療(お薬など)、リハビリテーション、診断書すべてのことを有国家資格者である医師にて提供することができます。整骨院・接骨院では応急処置のみ保険適応となり、診断書の発行、後遺症診断の発行はできません。
当院は整形外科専門医が診察を行っており、自賠責保険にて診療可能ですので、些細な症状でもお気軽に受診ください。
交通事故で
整形外科と整骨院・接骨院の
併用できる?
整形外科は当然、医療機関であるため、レントゲンやMRIなどの検査を受け、診断に基づいた適切な治療を受けることができます。しかしながら整骨院・接骨院では診断はできずお薬の投与も受けることができず、治療はなく施術のみとなります。
1回の診察ですべてのことがわかることは少なく、はじめと違う場所の痛みが出た場合、診察が必要となりますが、整骨院では診察を受けることはできず、レントゲン検査、MRI検査などが必要になった時には手遅れになる可能性があります。
自賠責保険を利用して整形外科と整骨院・接骨院を併用することは、条件つきで可能となっています。
ただし、いくつかの注意点があります。
医師の指示や同意: 脱臼や骨折に対する整骨院・接骨院の施術は、応急手当の場合を除き、原則として医師の同意が必要です。
※当院では例外なく整骨院への指示書は発行いたしておりません。
後遺障害診断書: 後遺障害が残った場合、後遺障害診断書を作成できるのは医師のみです。整骨院・接骨院のみに通院していた場合、後遺障害等級認定申請に必要な診断書を作成してもらうことができません。そのため、最終的な後遺障害の評価のためには整形外科への通院が重要となります。
労災保険もしくは自賠責保険で治療をうけられるかは患者さんと会社にて話し合いが必要になることがあります。会社(労災担当者)に相談し、労災保険、自賠責保険の適用についてご確認ください。
交通事故治療の流れ
1警察への届け出
まず事故担当所轄警察に電話をして届け出をして、指示に従ってください。
その際、交通事故証明書など必要書類(当院には提出不要です)を受け取ってください。
2保険会社とのやりとり
相手方の保険会社からの電話がありましたら、当院での治療希望をお伝えください。保険会社ごとに若干の流れの違いがありますので、事故後の流れについて保険会社からご説明があることがほとんどですので、説明がなければ保険会社へ再度ご連絡していただき、説明をうけてください。
治療については当院から整骨院等への指示書などの発行は例外なく行っておりません。また、交通事故後、整骨院に通われている患者さんの診断書発行のみの受診は受け付けておりません。保険会社と当院が直接やり取りすることはできかねますため、患者さんと保険会社にて連絡をお願いします。
3治療について
定期的な診察・検査・リハビリテーションにて治療を行います。
交通事故の経過として、はじめはなかった症状が後になって症状が出てくることが多いです。捻挫などは体表に変化が出にくく、他覚的にわからないこともありますので、新たな症状が出たら、再診予約の際に必ず問診記入をお願いします。
リハビリテーション
症状改善には理学療法士による施術による痛みの改善が一番良いかと思いますが、お仕事の都合などで日程がわかりづらいこともあるかと思います。その際は予約なしでもリハビリテーション機械を使ったリハビリテーションを受けていただくことで症状改善しやすくなることも多いです。
おおよそ3-6か月で症状固定の時期は来ますので、可能な範囲で診察、リハビリテーションを受けられることをおすすめします。
通院慰謝料について
慰謝料は不幸にも交通事故にあわれた患者さんを救済する補償制度の一つです。自賠責保険の通院慰謝料が1日通院ごとに支払われます。交通費も対象となることもありますので、交通費などの領収書を保存されることをお勧めします。詳細は保険会社の担当の方にお尋ねください。
4後遺症について
ある程度時間が経過すると保険会社より症状固定の連絡がきます。
症状固定とは完全に治った状態を指さず、症状がこれ以上改善せず、小康状態であることを指します。この判断には医療として疑問があるケースもありますが保険会社さん判断に依るところがほとんどです。
患者さんが納得いかない場合には患者さんの保険等に付帯する弁護士特約などを使われ弁護士と保険会社で話し合われる場合もあります。
後遺症診断書の作成が必要であれば当院で作成可能です。
5症状固定後の通院について
症状固定後は保険会社からの支払いは終了し、一切の支払いがなくなります。
支払い終了後もリハビリテーション等の継続を希望さあれば患者さんご自身の保険(健康保険)などを使っての通院となります。
診断書について
交通事故後、保険会社への手続きや、治療費の請求など、様々な場面で「診断書」が必要となります。この診断書は、患者さんの怪我の状態や治療内容などを記録したものです。
一例として
- 怪我の状態や診断結果
- 受けられた治療の内容と期間
- 通勤・通学などが可能か
などの内容を記載します。
ただしこちらは事故された当初に記載するものとなり、遅くても事故後10日以内に提出されることが多い印象です。
診断書についてご不明な点がございましたら受付までお申し付けください。
| 警察届出診断書作成料金 | 3,000円(税抜) |
|---|---|
| 自賠責保険等への提出用診断書 | 5,000円(税抜) |
| 後遺症診断書 | 8,000円(税抜) |
診断書類はすべて約1週間以内にお渡しとなります。お急ぎの場合は別料金になりますので、受付にお申し出ください。
注意
診断書発行、お渡し後に不要となった場合、診断書返却されても返金はいたしかねます。お渡し前に患者さんにて十分に確認された上で診断書依頼をお願いします。
また、お渡し後、患者さんにおかれましても日付などをご確認されたうえでお持ち帰りをお願いします。
日常生活についての注意点
道路交通法第70条第1項
「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と記されています。 そのため怪我の状態、痛みなどの自覚症状によっては運転を控えていただく必要があります。
就労
就業に関する命令に関してはお勤めの会社の就業規則に則って責任者の方が判断をされます。詳細な内容についてはそれぞれの会社によって異なりますので、お勤めの会社のご担当者と相談をお願いします。判断材料の一つとして、必要であれば診断書を発行しお手伝いさせていただきますので、お気軽にお申し出ください。
労災とは
 「労災(ろうさい)」とは、「労働災害(ろうどうさいがい)」の略称で、労働者が仕事中や通勤中に負ったケガなどのことを指します。
「労災(ろうさい)」とは、「労働災害(ろうどうさいがい)」の略称で、労働者が仕事中や通勤中に負ったケガなどのことを指します。
労災が発生した場合、労働者は労災保険という国の制度から必要な給付を受けることができます。
労災保険は、労働者の保護を目的とした公的な保険制度で、健康保険とは異なります。
当院は労災指定医療機関ですので安心して当院を受診ください。
労災で何日休める?
労災で休める期間には、法律上の明確な上限はありません。
労災による休業補償給付は、以下のいずれかの状態になるまで支給されます。
治癒
(症状が完全に良くなった状態)
医師が症状固定と判断し、治療の必要がなくなると支給は終了します。
症状固定
症状が安定し、これ以上治療を続けても改善が見込めないと労災基準監督署ら判断された場合、休業補償給付は打ち切られます。多くの場合、時期が近付けば労災担当の方から連絡が来ますので、連絡を受けられましたら適宜質問、ご相談されることをお勧めします。
重要なポイント
休業補償給付の支給開始
労災で休業した場合、最初の3日間は待機期間となり、労災保険からの休業補償給付は支給されません。
4日目から支給
労災保険からの休業補償給付は、休業4日目から支給されます。
医師の診断が重要: 休業の必要性や期間は、医師の診断に基づいて判断されます。漫然と休めるわけではありません。
復職の意思
症状が改善し、医師から就労可能との判断が出た場合は、原則として復職する必要があります。
当院は一方的に就労可能、不可能を判断することはなく、患者さんと相談して方針を決定します。ただし、診断書等については公的書類のため患者さんの希望通りに書くことを保証するものではないことをあらかじめご了承ください。
労災治療の流れ
- 受診前に職場の労災担当の方へ連絡・確認され、それでもわからないことは所轄の労働基準署または労働局労災補償課へ連絡いただき、今後の流れについて確認をされた方が良いことが多いです。
- 当院を受診時には労災で受診することを事前問診に書いていただき、受診時に受付でもお伝えください。(患者さんご自身の健康保険で受診された場合、非常に手続きが難渋し、患者さんの治療に差し障りますのでご注意ください。)
- 定期的な診察およびリハビリテーションが重要です。並行してたくさん書類が患者さんに届きますので、会社の担当の方と相談いただき、必要な書類を当院へお持ちください。
労災保険を使用しての診療リハビリテーションについては窓口での支払いはありません(ただし初回受診に関しては患者さんによる立て替えが必要になる場合がまれにあります。この場合、後日受診時に返金となることがほとんどです。) - 労災保険による診療を受けている場合、会社の担当の方へ定期的な報告および書類の指示をうけてください。
- 交通費(移送費)について一定の条件を満たせば、支給されることがありますので領収書などを置いておくことをお勧めします。(当院への提出は不要です)
- 不明な点は会社の担当の方や労働基準監督署へ相談をお勧めします。
手続きを委託する場合は、社会保険労務士へ相談することもできます。
労災保険の各種給付についての支給、不支給の決定は労働基準監督署長が行います。
注意点が何点かあります。
- 休業補償の打ち切り: 労働基準監督署は、被災労働者の症状が治癒(症状固定を含む)し、労働が可能になったと判断した場合、休業補償給付を打ち切ります。
- 療養(補償)給付の打ち切り: 治療が終了した場合や、症状が固定し、治療の必要がなくなったと判断された場合、療養(補償)給付は打ち切られます。
- 労災保険の給付打ち切りは、あくまで労働基準監督署の判断となります。
労災保険とは、労働者災害補償保険法に基づく日本の公的保険制度です。
主に、労働者が業務上の理由または通勤によって負傷、障害を負ったりした際に必要な保険給付を行うものです。
まず、業務内でのケガであるかはそれぞれの会社の担当の方に相談ください。
受診をご希望される場合、当院窓口で労災保険での受診であることをお伝えください。
特殊な場合を除き、支払いにおいて自己負担はありません。
もし、健康保険から労災保険に切り替える場合は早めに行うと自己負担および、患者さんご自身で作成する複雑な書類の提出をまぬがれることができることが多いです。
労災保険への切り替えが遅れた場合の複雑な費用返還手続きは当院では代行できませんので患者さんご自身で行っていただくことになります。
なお、労災保険は基本的に健康保険との併用はできません。そのため、労災保険で受診された同日には、持病の検査、治療等はできませんのでご注意ください。
自賠責保険支払いについて
 自賠責保険(交通事故の保険)正式名称は「自動車損害賠償責任保険」といい、自動車やバイク(原付含む)を運行する際に、法律によって加入が義務付けられている強制保険です。
自賠責保険(交通事故の保険)正式名称は「自動車損害賠償責任保険」といい、自動車やバイク(原付含む)を運行する際に、法律によって加入が義務付けられている強制保険です。
自賠責保険の主な目的は、交通事故の被害者を救済することです。交通事故で他人を死傷させてしまった場合、加害者が十分な賠償金を支払えないといった事態を防ぎ、被害者(患者さん)に対して最低限の補償を行うことを目的としています。
交通事故には書類関係が多く発生します。患者さんにて用意いただき、お持ちいただければ作成しますのでお気軽にご提出ください。1週間程度で作成いたします。
交通事故関連の支払いについての様々な決まりがあるため、以下支払いについて記述いたします。
健康保険を併用する場合、自賠責保険もしくは任意保険会社が直接支払う場合(一括対応)、それぞれ利点、欠点があります。
一括支払い対応には上限はあるものの治療の全額支払いが保険会社と病院との直接交渉となるため、立て替えの必要がほぼなく(例外的に発生する場合があります)支払い手続きの簡便が利点です。しかしながら自賠責保険には上限があり、それを超える分は任意保険対応となります。また、民間保険会社が治療内容等を決めるため、制限が生じます。
また民間保険会社からの不払い、支払い遅延があった場合は、患者さんに立て替えてもらい患者さんから保険会社へ請求してもらう場合もあります。
健康保険併用での支払いを選択される場合は稀です。
自賠責保険の上限およびご自身の健康保険で治療することができ、長期治療することができるという利点があります。しかしながら患者さん自身ですべての手続きを行う必要があり、事前に保険者(国民健康保険、健康保険組合など保険証に書いてある保険者)へ交通事故の使用許可を得てからとなります。
この場合、当院での治療費請求代行は一切できませんので、患者さんご自身ですべての手続きを行っていただくことになります。
それぞれ利点、欠点がありますので、患者さんに選択いただくこととなります。
- 保険会社の示談交渉: 交通事故など第三者の行為が原因の労災の場合、加害者側の保険会社が治療費の打ち切りなどを打診してくることがありますが、当院は医療の提供のみとなり、費用・書類の交渉はできませんことを予めご了承ください。